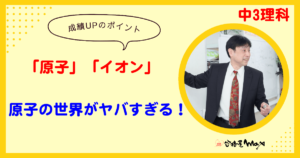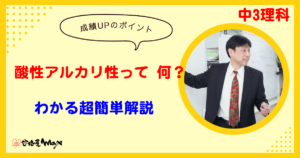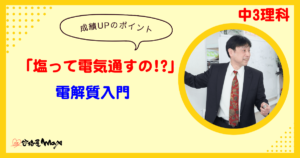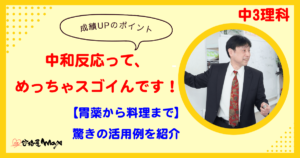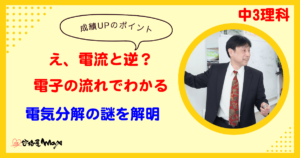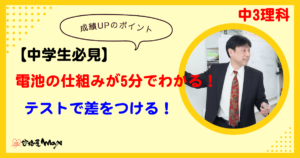みんなは「光」って不思議だと思ったことない?
今回は、中学理科で習う「光」の単元を、イラスト多めでわかりやすく解説していくよ!
光の進み方
光は目に見えないけど、まっすぐ進む性質があるんだ。懐中電灯の光がまっすぐ伸びるのを見たことあるよね?あれは光が直進しているからなんだ。
でも、光は違う物質に入るときに、進む方向を変えることがあるんだ。これが 屈折 と呼ばれる現象だよ。
例えば、水が入ったコップにストローを入れると、曲がっているように見えるよね? あれは、光が空気中から水中に入る時に屈折するせいで、私たちの目に錯覚を起こさせているんだ!
鏡に映る? 反射の法則
光は鏡などで跳ね返るよね?これを 反射 というよ。 光が反射するときには、必ず「入射角」と「反射角」が等しくなるんだ。これを 反射の法則 というよ。
マックス流! 屈折の法則攻略! 光の道筋をマスター!
光が水に入るとき、折れ曲がって見えるよな? あれは光の屈折ってやつだ!
でも、どっちに曲がるのか、迷ったりしてませんか?
大丈夫!マックス流! 屈折の法則なら、超簡単にマスターできます!
【マックス流 屈折の法則】
ポイントは光の速度変化だ!
法則1: 速度ダウン!⇒ 垂直線に接近!
光は、空気中よりも水中の方が進むのが遅くなる。
だから、空気中から水中に入るとき、光は進むのが遅くなって、境界面の垂直線に近づこうとするんだ!
法則2: 速度アップ!⇒ 垂直線から離脱!
逆に、水中から空気中に出るときは、光は進むのが速くなる。
だから、境界面の垂直線から遠ざかろうとするんだ!
【図解】
- まずは、光が水中に入る点で、境界面に垂直な線(垂直線)を引く。
- 光が空気中から水中に入るときは、垂直線に近づくように光を曲げる。
- 水中から空気中に出ていくときは、垂直線から遠ざかるように光を曲げる。
覚え方!
- 速度ダウン!⇒ 垂直線大好き!
- 速度アップ!⇒ 垂直線から逃げる!
どうだ!簡単だろ?
この法則を覚えれば、もう光の屈折問題は怖くない!
テストで高得点も夢じゃないぜ!
凸レンズってどんなレンズ?
レンズには大きく分けて「凸レンズ」と「凹レンズ」の2種類があるんだけど、今回は 凸レンズ に注目するよ!
凸レンズは、真ん中が膨らんだ形をしたレンズで、光を集める働きがあるんだ。虫眼鏡を使ったことある?あれは凸レンズを使って、太陽の光を集めてるんだよ。
凸レンズの魔法!光の進路を変えてみよう!
凸レンズは光の進路を変えることができるんだ。その性質は、主に3つ!
- 光軸に平行に進む光は、焦点を通る。
- 焦点を通った光は、光軸に平行に進む。
- レンズの中心を通った光は、直進する。
これらの性質を利用することで、凸レンズはものを大きく見せたり、反対に見せたりすることができるんだ!
凸レンズ攻略! マックス流 実像の法則!
凸レンズの実像って、作図するのめんどくせぇよな?
でも、大丈夫!このマックス流 実像の法則さえ覚えれば、作図なんかしなくても、実像の特徴がパパッと分かっちゃうんだぜ!
マックス流 実像の法則!
ポイントは焦点距離との距離だ!
【法則1】 2倍の壁を越えろ!
物体とレンズの距離が、焦点距離のちょうど2倍のときが境目だ!
この壁を境目に、実像の大きさや位置が変わってくるんだぜ!
【法則2】 遠ければ小さく、近ければ大きく!
- 焦点距離の2倍より遠くに行けば行くほど、実像は小さく、レンズに近づいていく。
- 逆に、焦点距離に近づけば近づくほど、実像は大きく、レンズから遠ざかっていくんだ。
【法則3】 2倍の位置はシンメトリー!
物体とレンズの距離が焦点距離のちょうど2倍のときだけは特別だ!
実像はレンズの反対側の焦点距離の2倍の位置に、物体と同じ大きさで出現する。
完璧なシンメトリーってやつだ!
このマックス流 実像の法則を覚えれば、もう凸レンズの実像問題は怖くない!
テストで高得点も夢じゃないぜ!
どうだ、この法則を使えば、凸レンズマスターになれる!
まとめ
今回は光の性質、特に凸レンズについて詳しく見てきたけど、どうだったかな?
身の回りには、光を利用したものがたくさんあるよ!
今回の内容を参考に、身の回りの光について、もっと深く探求してみてね!
光のヒミツを探れ! 理解度チェック問題!
「光」の単元から、20問の理解度チェック! 全問正解目指してがんばろう!
① 光は、まっすぐに進む性質があります。この性質を何といいますか。
⑴ 光の屈折
⑵ 光の反射
⑶ 光の直進
⑷ 光の散乱
② 光が鏡などで跳ね返る現象を何といいますか。
⑴ 光の屈折
⑵ 光の反射
⑶ 光の直進
⑷ 光の散乱
③ 光が空気中から水中に入るときのように、異なる物質の境界面で光が曲がる現象を何といいますか。
⑴ 光の屈折
⑵ 光の反射
⑶ 光の干渉
⑷ 光の回折
④ 反射の法則とは、入射角とどの角度が等しいという法則ですか?
⑴ 屈折角
⑵ 反射角
⑶ 臨界角
⑷ 位相角
⑤ 光がすべて反射されてしまう現象を何といいますか?
⑴ 全反射
⑵ 全屈折
⑶ 鏡面反射
⑷ 乱反射
⑥ 凸レンズは、光を何といいますか?
⑴ 集める
⑵ 散乱させる
⑶ 反射する
⑷ 吸収する
⑦ 凸レンズの中心を通る直線を何といいますか?
⑴ 光軸
⑵ 焦点
⑶ 焦点距離
⑷ 像
⑧ 凸レンズを通った光が再び1点に集まる点を何といいますか?
⑴ 光軸
⑵ 焦点
⑶ 焦点距離
⑷ 像
⑨ 焦点から凸レンズまでの距離を何といいますか?
⑴ 光軸
⑵ 焦点
⑶ 焦点距離
⑷ 像
⑩ 物体と凸レンズの距離が焦点距離より短い場合、どのような像ができますか?
⑴ 実像
⑵ 虚像
⑪ 物体と凸レンズの距離が焦点距離より長い場合、どのような像ができますか?
⑴ 実像
⑵ 虚像
⑫ 実像は、スクリーンに映せる?映せない?
⑴ 映せる
⑵ 映せない
⑬ 虚像は、スクリーンに映せる?映せない?
⑴ 映せる
⑵ 映せない
⑭ 実像は、物体に対して上下左右どのように見えますか。
⑴ 上下左右同じ
⑵ 上下逆さま、左右同じ
⑶ 上下同じ、左右逆
⑷ 上下逆さま、左右逆
⑮ 虚像は、物体に対して上下左右どのように見えますか。
⑴ 上下左右同じ
⑵ 上下逆さま、左右同じ
⑶ 上下同じ、左右逆
⑷ 上下逆さま、左右逆
⑯ 虫眼鏡は、凸レンズの何の性質を利用していますか?
⑴ 光を集める性質
⑵ 光を拡散する性質
⑶ 光を反射する性質
⑰ カメラは、凸レンズの何の性質を利用していますか?
⑴ 実像を作る性質
⑵ 虚像を作る性質
⑱ プロジェクターは、凸レンズの何の性質を利用していますか?
⑴ 実像を作る性質
⑵ 虚像を作る性質
⑲ 望遠鏡は、凸レンズの何の性質を利用していますか?
⑴ 物体を拡大して見せる性質
⑵ 物体を縮小して見せる性質
⑳ 顕微鏡は、凸レンズの何の性質を利用していますか?
⑴ 物体を拡大して見せる性質
⑵ 物体を縮小して見せる性質
解答と解説
① (3) 光の直進
解説:光は、障害物がなければまっすぐに進む性質があります。
② (2) 光の反射
解説:光が鏡など、滑らかな表面で跳ね返る現象を光の反射といいます。
③ (1) 光の屈折
解説:光は、異なる物質の境界面を通過する際に、その速度が変化するため屈折が起こります。
④ (2) 反射角
解説:反射の法則は、「入射角=反射角」で表されます。
⑤ (1) 全反射
解説:光が、屈折率の大きい物質(例:水)から小さい物質(例:空気)へ進むとき、入射角がある一定の角度を超えると、光がすべて反射される現象です。
⑥ (1) 集める
解説:凸レンズは、真ん中が厚いレンズであり、光を集める性質を持っています。
⑦ (1) 光軸
解説:凸レンズの中心を通る直線を光軸といいます。
⑧ (2) 焦点
解説:凸レンズを通った光が再び1点に集まる点を焦点といいます。
⑨ (3) 焦点距離
解説:焦点から凸レンズまでの距離を焦点距離といいます。
⑩ (2) 虚像
解説:物体と凸レンズの距離が焦点距離より短い場合、レンズを覗くと、反対側に拡大された虚像が見えます。
⑪ (1) 実像
解説:物体と凸レンズの距離が焦点距離より長い場合、レンズを通過した光が実際に集まってできる像、つまり実像ができます。
⑫ (1) 映せる
解説:実像は、光が実際に集まってできる像なので、スクリーンに映すことができます。
⑬ (2) 映せない
解説:虚像は、光が実際に集まっているのではなく、レンズを通った光を延長した線上にできる像なので、スクリーンに映すことはできません。
⑭ (4) 上下逆さま、左右逆
解説:実像は、物体に対して上下左右が反転した像として映ります。
⑮ (1) 上下左右同じ
解説:虚像は、物体と上下左右が同じ向きに拡大された像として見えます。
⑯ (1) 光を集める性質
解説:虫眼鏡は、凸レンズを用いて太陽光を集め、一点を高温にすることで火をおこしたり、物を熱したりするために使われます。
⑰ (1) 実像を作る性質
解説:カメラは、凸レンズを用いて、被写体の光をフィルムやセンサーに集め、実像を記録する装置です。
⑱ (1) 実像を作る性質
解説:プロジェクターは、凸レンズを用いて、映像を拡大してスクリーンに投影する装置です。投影される映像は実像です。
⑲ (1) 物体を拡大して見せる性質
解説:望遠鏡は、遠くにある物体を観察するために用いられる装置で、凸レンズの組み合わせによって、物体を拡大して見せることができます。
⑳ (1) 物体を拡大して見せる性質
解説:顕微鏡は、肉眼では見えない微小な物体を観察するために用いられる装置で、凸レンズの組み合わせによって、物体を拡大して見せることができます。
😊「なんだ。簡単じゃん」と感じてもらえたらすごくうれしいです。わかりにくい問題があったら、教えてください。簡単に説明したり、わかりやすい他の方法で、もっと楽に理解が深まります。
「ブログより実際に話しがしたい」「もっといろいろ教えてほしい!」と感じた人は、無料体験や相談に来てください! この先生に相談をすることや習うことができます! 少し勇気を出して、ぜひ一度体験しに来てください! 「わかるって面白い」とか成績が良くなる自分を感じられる日がきます。お問い合わせ・ご質問はこちらです。


◆鶴ヶ谷教室 ☎252-0998
989-0824 宮城野区鶴ヶ谷4-3-1
◆幸 町 教室 ☎295-3303
983-0836 宮城野区幸町3-4-19
電話でのお問合せ AM10:30~PM22:30
【物理】もう光は怖くない!マックス流 光の法則でテストを制覇せよ!
よぉ、受験生諸君!光の単元で苦戦してねぇか?
「光の直進」「反射の法則」「屈折の法則」…教科書見てもピンとこねぇって?
安心しろ!俺、マックスがわかりやすく解説してやる!
今回は、特に重要な**「凸レンズの実像」と「光の屈折」**について、俺が編み出したオリジナルの法則を伝授するぜ!
凸レンズ攻略!マックス流 実像の法則!
凸レンズの実像の位置と大きさ、作図するのめんどくせぇよな?
でもよ、大丈夫!この法則さえ覚えれば、作図なんかしなくても、実像の特徴がパパッと分かっちゃうんだぜ!
【マックス流 実像の法則】
ポイントは焦点距離との距離だ!
法則1: 2倍の壁を越えろ!
物体とレンズの距離が、焦点距離のちょうど2倍のときが境目だ!
この壁を境目に、実像の大きさや位置が変わってくるんだぜ!
法則2: 遠ければ小さく、近ければ大きく!
- 焦点距離の2倍より遠くに行けば行くほど、実像は小さく、レンズに近づいていく。
- 逆に、焦点距離に近づけば近づくほど、実像は大きく、レンズから遠ざかっていくんだ。
法則3: 2倍の位置はシンメトリー!
物体とレンズの距離が焦点距離のちょうど2倍のときだけは特別だ!
実像はレンズの反対側の焦点距離の2倍の位置に, 物体と同じ大きさで出現する。
完璧なシンメトリーってやつだ!
このマックス流 実像の法則を覚えれば、もう凸レンズの実像問題は怖くない!
テストで高得点も夢じゃないぜ!
マックス流!屈折の法則攻略!光の道筋をマスターしろ!
次は、光が水に入るときみたいに、折れ曲がって見える「光の屈折」だ!
どっちに曲がればいいか、迷ったりしないか?
大丈夫!マックス流!屈折の法則なら、超簡単にマスターできるぜ!
【マックス流 屈折の法則】
ポイントは光の速度変化だ!
法則1: 速度ダウン!⇒ 垂直線に接近!
光は、空気中よりも水中の方が進むのが遅くなる。
だから、空気中から水中に入るとき、光は進むのが遅くなって、境界面の垂直線に近づこうとするんだ!
法則2: 速度アップ!⇒ 垂直線から離脱!
逆に、水中から空気中に出るときは、光は進むのが速くなる。
だから、境界面の垂直線から遠ざかろうとするんだ!
覚え方!
- 速度ダウン!⇒ 垂直線大好き!
- 速度アップ!⇒ 垂直線から逃げる!
どうだ!簡単だろ?
この法則を覚えれば、もう光の屈折問題は怖くない!
テストで高得点も夢じゃないぜ!
まとめ
今回は「凸レンズの実像」と「光の屈折」について、俺のオリジナル法則を伝授した!
もう、難しい公式や作図は覚えなくていい!
このマックス流法則で、光の単元をマスターして、テストで高得点ゲットだぜ!
応援してるぜ、未来の物理学者たち!
光の世界を探検しよう!~凸レンズ編~
みんなは「光」って不思議だな~と思ったことない?
今回は、中学理科で習う「光」の単元から、特に凸レンズに焦点を当てて、図や例題を用いながらわかりやすく解説していくよ!
光の性質
光には、
- 直進:まっすぐ進む
- 反射:鏡などで跳ね返る
- 屈折:物質が変わるときに曲がる
という3つの性質があるんだ。
例えば、懐中電灯の光がまっすぐ進むのは「直進」、鏡に自分が映るのは「反射」、水に入ったストローが曲がっているように見えるのは「屈折」の性質によるものなんだ。
凸レンズってどんなレンズ?
レンズには大きく分けて「凸レンズ」と「凹レンズ」があるけど、今回は 凸レンズ に注目するよ!
凸レンズは、真ん中が膨らんだ形をしたレンズで、光を集める働きがあるんだ。 虫眼鏡を太陽にかざすと、一点に光が集まって熱くなるよね?あれは凸レンズの働きによるものなんだ。
凸レンズの魔法!光の進路を変えてみよう!
凸レンズは、光をある一点に集めたり、光の進路を変えたりすることができるんだ。
その性質は、主に3つ!
- 光軸に平行に進む光は、焦点を通る。
- 焦点を通った光は、光軸に平行に進む。
- レンズの中心を通った光は、直進する。
これらの性質を理解することが、凸レンズで起こる現象を理解する上でとても重要になるよ!
凸レンズの実像と虚像
凸レンズは、物体から出た光を集めて、スクリーンなどに像を映し出すことができるんだ。
スクリーンに映し出せる像を 実像、スクリーンに映し出せない像を 虚像 というよ。
実像と虚像は、凸レンズと物体の距離によって、できる場所や見え方が変わるんだ。
| 実像 | 虚像 | |
| 特徴 | スクリーンに映せる | スクリーンに映せない |
| 上下左右 | 上下左右反対 | 上下左右同じ |
| 大きさ | 物体より大きくも小さくもなる | 物体より大きく見える |
| 位置 | レンズの反対側 | レンズの物体側 |
身近にある凸レンズ
凸レンズは、私たちの身の回りで色々なものに使われているんだ。
- 虫眼鏡: 光を集めて物を大きく見せる
- カメラ: 光を集めて像をフィルムやセンサーに焼き付ける
- 望遠鏡: 遠くの物を大きく見せる
- 顕微鏡: 小さな物を大きく見せる
凸レンズは、私たちの生活を豊かにするのに役立っているんだね!
まとめ
今回は、光の性質、凸レンズの働きについて学んできたけどどうだったかな?
凸レンズは、光を操ることができる不思議な道具なんだ。
身の回りにある光を利用した製品をよく観察して、その仕組みを考えてみると、もっと光のことが面白くなるよ!
光の不思議な現象!屈折と全反射を解き明かそう!
光はまっすぐ進む性質を持っているけど、実は物質と物質の境界面では、進む方向を変えることがあるんだ。これが 屈折 と呼ばれる現象だよ。
そして、ある条件下では光が全て反射してしまう 全反射 という現象も起こるんだ。
今回は、光の屈折と全反射について、詳しく見ていこう!
光の屈折:進む速さが変わる?!
光は、物質によって進む速さが違うんだ。例えば、光は空気中よりも水中の方が進むのが遅くなる。
光が空気中から水中に入るときのように、進む速さが異なる物質の境界面を通過する際に、光の屈折は起こるんだ。
屈折の法則:垂直線に近づく?離れる?
光の屈折には、以下の法則があるよ。
- 入射角と屈折角: 光が境界面で曲がる角度には、規則性があるんだ。入射角を大きくすると屈折角も大きくなるけど、その比率は物質によって決まっているんだ。
- 速さと屈折する方向: 光は、進むのが遅くなる物質に入るときは、境界面に垂直な線(法線)に近づくように屈折する。逆に、速くなる物質に入るときは、法線から遠ざかるように屈折するんだ。
身近な屈折現象
- 水中の魚の位置がずれて見える
- ストローが水を入れたコップの中で折れ曲がって見える
- 空気中の光が水滴で屈折することで虹ができる
これらの現象は、光の屈折によって起こる現象なんだ。
光の全反射:鏡のように全て反射!?
光が物質の境界面で全て反射される現象を 全反射 というよ。
全反射の条件
全反射は、以下の条件が満たされたときに起こるんだ。
- 光が、屈折率の大きい物質から小さい物質に進むとき。
- 例:水から空気、ガラスから空気
- 入射角が、ある一定の角度(臨界角)よりも大きいとき。
身近な全反射現象
- 光ファイバー:光信号を遠距離まで伝えるために利用されている。
- ダイヤモンドの輝き:ダイヤモンドは高い屈折率を持つため、内部で全反射を繰り返して輝いて見えるんだ。
まとめ
今回は、光の屈折と全反射について解説したよ!
これらの現象は、私たちの身の回りで様々なところで役立っているんだ!
- 光ファイバーによる高速通信
- 内視鏡による体内観察
- カメラのレンズ
などなど、光は私たちの生活を支えるために、色々な場面で活躍しているんだね!
ぜひ、身の回りの現象と関連付けながら、光の不思議について考えてみてね!
鏡の世界に挑戦!見える範囲マスターになろう!
鏡は、身の回りに当たり前にあるものだけど、改めて考えると不思議がいっぱい!
特に「鏡で見える範囲」は、テストでもよく出るんだけど、混乱しやすいポイントなんだ。
そこで今回は、鏡の見える範囲について、一緒にマスターしていこう!
ポイント1: 鏡に映るのは「光」!
鏡に物が映って見えるのは、物体が反射した光が、鏡で反射して、私たちの目に届いているからなんだ。
ポイント2: 反射の法則を思い出せ!
鏡の反射は、「入射角」と「反射角」が等しくなる 反射の法則 に従っている。これを意識するのが、見える範囲を正確に捉えるためのカギとなるぞ!
問題に挑戦!
では早速、例題を通して理解を深めていこう!
【例題】
図のように、身長140cmの鏡子が、高さ200cmの鏡から2m離れて立っています。
(1) 鏡子の全身を映すためには、最低でもどれだけの高さの鏡が必要ですか?
(2) 鏡子が鏡に近づくと、見える範囲はどうなりますか?
【解答と解説】
(1) 全身を映すために必要な鏡の高さは、鏡子の身長の半分で十分なんだ。
* なぜなら、頭頂部や足先から出た光が鏡で反射して目に届くためには、身長の半分の高さがあれば足りるからだよ!
答え: **70cm**(2) 鏡子が鏡に近づくと、見える範囲は 広くなる!
* 鏡から遠い位置にあるものほど、鏡に映る範囲は狭くなる。
* 逆に、鏡に近づけば近づくほど、より広い範囲を映すことができるんだ!まとめ
今回は、鏡で見える範囲について考えてみたけど、どうだったかな?
- 鏡に映るのは「光」であること
- 「反射の法則」に従って光が反射していること
この2点を意識することで、鏡の問題を解くカギになるはずだ!
鏡は、奥が深い! 身近なものを使って、色々な角度から観察して、更なる発見を目指そう!