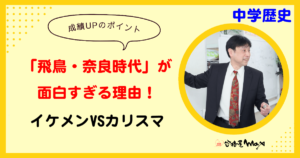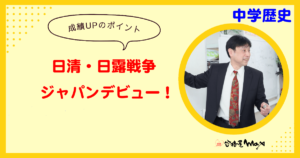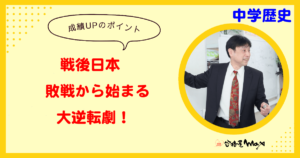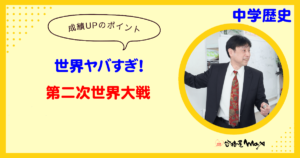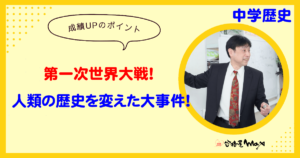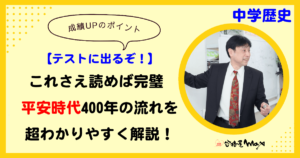【中学生のための爆わかり歴史ブログ】江戸時代の最強支配システムを完全攻略!
やっほー!歴史の勉強、がんばってる?
前回、天下統一を成し遂げた豊臣秀吉。でも、彼が亡くなった後、虎視眈々とチャンスを狙っていた男がいた…。
そう、ついにラスボス、徳川家康(とくがわいえやす)の登場だ!
今日から始まるのは、約260年も続く平和な時代「江戸時代」!
でも、どうしてそんなに長く平和が続いたんだろう?
この時代のテーマは、ズバリこれ!
【ケンカはもう終わり!ガチガチのルールで全国を支配する!】
家康が作った、最強の支配システムを一緒に見ていこう!
第1章 江戸幕府、爆誕!
1600年、天下分け目の「関ヶ原の戦い」
秀吉の死後、次の天下人の座をかけて、徳川家康(東軍) vs 石田三成(西軍)の最終決戦が勃発!
この関ヶ原の戦いに勝利した家康が、ついに日本のトップに立つ!
そして1603年、家康は征夷大将軍となり、江戸(今の東京)に江戸幕府を開いたんだ。
鎌倉・室町幕府と違って、スタート時点でもう敵がいない、日本史上最強の幕府の誕生だ!
第2章 これが最強の支配システム「幕藩体制」だ!
江戸幕府が260年以上も続いたヒミツは、この「幕藩体制(ばくはんたいせい)」という超絶巧みな仕組みにある。
① 大名を3種類にランク分け!
家康は、大名を自分との関係の近さで3つに分類し、巧みにコントロールした。
- 親藩(しんぱん):徳川家の親戚。
- 譜代大名(ふだいだいみょう):昔からのダチや家来。幕府の重要な仕事(老中など)を任せる。
- 外様大名(とざまだいみょう):関ヶ原で敵だったヤツら。常に監視!
② ガチガチの法律で全員をしばる!
幕府は、身分ごとに厳しいルールブックを作って、全国民をコントロールした。
- 武家諸法度(ぶけしょはっと):大名専用のルール。「勝手に城を修理するな!」「勝手に結婚するな!」と、力をつけさせないようにガチガチにしばる!
- 禁中並公家諸法度(きんちゅうならびにくげしょはっと):天皇・貴族専用のルール。「政治に口出ししないで、学問だけやっててね!」と、行動を制限。
③ 参勤交代でヘトヘトにさせる!
これが一番エグい!参勤交代!
すべての大名は、1年おきに自分の領地と江戸を大名行列で往復。マジでお金がかかる!
さらに、奥さんと子供は江戸に人質として住まわせる。
これで、大名たちは幕府に逆らうお金もヒマも、そして度胸もなくなっちゃうってワケだ。
④ 考え方までコントロール!「朱子学」
幕府は、「上下関係は絶対!身分は守ろう!」と教える朱子学(しゅしがく)を公式な学問にした。
考え方まで幕府のルールに染め上げることで、反乱が起きないようにしたんだ。
第3章 鎖国への道 ― 貿易とキリスト教
最初は貿易してた!?「朱印船貿易」
家康は、最初から国を閉じていたわけじゃない。
むしろ、幕府の許可証(朱印状)を持った船に、東南アジアとの貿易(朱印船貿易)をガンガンやらせてたんだ。でも、キリスト教の広まりを恐れて、やがてこの朱印船貿易も禁止され、日本人の海外渡航は全面的にストップされることになる。
なぜキリスト教を禁止したの?
でも、幕府はだんだんキリスト教をヤバいと思うようになる。
理由は2つ!
- 「神の前ではみな平等」という教えが、士農工商の身分制度と合わない!
- スペインとかが、布教をしながら国を乗っ取る(植民地化)のを警戒した!
幕府をビビらせた「島原・天草一揆」
1637年、厳しい年貢とキリスト教弾圧に苦しんだ人々が、天草四郎をリーダーに大反乱!
この島原・天草一揆にマジでビビった幕府は、ついに国を閉ざす決意をする。
「鎖国」の完成と4つの窓口
こうして、幕府が外国との交流を厳しく管理する「鎖国」体制が完成したんだ。
ヨーロッパとの窓口は、長崎の出島(でじま)だけに限定!相手は、キリスト教を広めないと約束したオランダと、昔からの付き合いの中国(清)だけになった。
【入試Point!】でも、完全に国を閉じたわけじゃない!幕府は「4つの窓口」で交流を続けていたんだ。
- 長崎口 →オランダ・中国(清)との貿易
- 対馬口(つしまぐち) → 朝鮮(将軍が代わるたびに朝鮮通信使が挨拶に来た)
- 薩摩口(さつまぐち) → 琉球王国(今の沖縄)
- 松前口(まつまえぐち) → アイヌ民族(今の北海道)
第4章 町人が主役!キラキラの元禄文化
260年も平和が続くと、戦争がないから武士より商人の方がお金持ちになる。
17世紀の終わりごろ、京都や大阪を中心に、町人が主役の元禄文化(げんろくぶんか)が花開いたんだ!
- 文学界のビッグ3!
- 松尾芭蕉(まつおばしょう):『おくのほそ道』で俳句を国民的アートにした旅人。
- 井原西鶴(いはらさいかく):町人のリアルな恋愛やお金の話を小説(浮世草子)にして大ヒットさせた作家。
- 近松門左衛門(ちかまつもんざえもん):人形浄瑠璃(今でいうアニメやドラマ?)の脚本で、みんなを泣かせた天才脚本家。
- アート界のスター!
- 菱川師宣(ひしかわもろのぶ)が浮世絵の版画を完成!町人でも気軽に買えるブロマイドみたいに大流行したんだ。
今日のまとめ!
- 徳川家康は、関ヶ原の戦いに勝利し、江戸幕府を開いた。
- 幕藩体制という、大名をランク分けし、武家諸法度や参勤交代でコントロールする最強の支配システムを作り上げた。
- 島原・天草一揆をきっかけに鎖国を完成させたが、「4つの窓口」で限られた国・地域とは交流を続けていた。
- 平和な世の中で町人が力をつけ、京都・大阪を中心に華やかな元禄文化が栄えた。
【江戸時代・前半】実力診断!確認テスト20
① 1600年、徳川家康が石田三成らを破り、全国の支配権を確立した戦いを何といいますか?
① 解答:関ヶ原の戦い(せきがはらのたたかい)
解説:この戦いの勝利で、徳川家康の天下が事実上決まりました。
② 徳川家康が征夷大将軍に任命され、江戸幕府を開いたのは西暦何年ですか?
② 解答:1603年
解説:ここから約260年間続く江戸時代がスタートします。
③ 幕府と、大名が治める藩とで全国を支配する江戸時代の仕組みを何といいますか?
③ 解答:幕藩体制(ばくはんたいせい)
解説:幕府と藩による二重の支配構造が、江戸時代の特徴です
④ 関ヶ原の戦いより前から徳川氏の家来だった大名を、特に何と呼びますか?
④ 解答:譜代大名(ふだいだいみょう)
解説:彼らは幕府の重要な役職(老中など)に就きました。関ヶ原の後に家来になったのは外様大名です
⑤ 幕府が、大名が勝手に城を修理したり結婚したりすることを禁じた法律は何ですか?
⑤ 解答:武家諸法度(ぶけしょはっと)
解説:大名が力をつけすぎないように、幕府が厳しくコントロールするためのルールブックです
⑥ 大名に1年おきに江戸と領地を往復させ、その妻子を江戸に住まわせた制度を何といいますか?
⑥ 解答:参勤交代(さんきんこうたい)
解説:大名にお金を使わせることで、経済的に力をつけさせない目的がありました。
⑦ 幕府が、天皇や公家(貴族)の行動を統制するために定めた法律は何ですか?
⑦ 解答:禁中並公家諸法度(きんちゅうならびにくげしょはっと)
解説:天皇や貴族が政治に口出しできないように、学問に専念することなどを定めました。
⑧ 江戸幕府が、上下関係や身分秩序を重んじる学問として武士に奨励した儒学の一派を何といいますか?
⑧ 解答:朱子学(しゅしがく)
解説:この教えが、士農工商という身分制度を思想面から支えました。
⑨ 江戸時代初期に、幕府の許可証(朱印状)を得た船が東南アジアと行った貿易を何といいますか?
⑨ 解答:朱印船貿易(しゅいんせんぼうえき)
解説:鎖国前は、幕府主導で海外との貿易を活発に行っていた時期があったことを押さえましょう。
⑩ 1637年、厳しい年貢とキリスト教弾圧に反発した人々が、天草四郎をリーダーとして起こした大規模な一揆を何といいますか?
⑩ 解答:島原・天草一揆(しまばら・あまくさいっき)
解説:この大規模な一揆に驚いた幕府が、鎖国へと舵を切る大きなきっかけとなりました。
⑪ 問⑩の一揆をきっかけに幕府が完成させた、外国との交流を厳しく制限する政策を何といいますか?
⑪ 解答:鎖国(さこく)
解説:キリスト教の禁止を徹底するための政策でした。
⑫ 鎖国中、ヨーロッパとの貿易が唯一許された、長崎に作られた人工島を何といいますか?
⑫ 解答:出島(でじま)
解説:オランダ商館が置かれ、ヨーロッパとの唯一の窓口となりました。
⑬ 鎖国政策のもとで、幕府が長崎での貿易を許可したヨーロッパの国はどこですか?
⑬ 解答:オランダ
解説:オランダはキリスト教の中でもプロテスタントで、カトリックと違って布教に熱心でなかったため、貿易が許可されました。
⑭ 人口の約85%を占める百姓(農民)を、5戸前後を1組として年貢などで連帯責任を負わせた制度を何といいますか?
⑭ 解答:五人組(ごにんぐみ)
解説:この制度によって、農民同士で監視させ、年貢の確実な徴収や反乱の防止を図りました
⑮ 江戸幕府の役職で、大名が就任する最高職であり、普段の政治を取り仕切った役職は何ですか?
⑮ 解答:老中(ろうじゅう)
解説:譜代大名の中から選ばれ、複数人で政治の重要な決定を行いました。
⑯ 17世紀末から18世紀初めにかけて、京都や大阪の町人を中心に栄えた、活気にあふれる文化を何といいますか?
⑯ 解答:元禄文化(げんろくぶんか)
解説:平和な時代が続き、経済的に豊かになった町人たちが文化の担い手となりました。
⑰ 「おくのほそ道」を著し、俳諧を芸術として高めた元禄文化の人物は誰ですか?
⑰ 解答:松尾芭蕉(まつおばしょう)
解説:彼は日本各地を旅しながら、多くの俳句を残しました。
⑱ 元禄文化のころ、町人の生活をリアルに描いた「浮世草子」という小説で人気を博した人物は誰ですか?
⑱ 解答:井原西鶴(いはらさいかく)
解説:『好色一代男』などの作品で、大阪の町人たちの生活を描きました。
⑲ 「曽根崎心中」など、人形浄瑠璃の脚本を書き、庶民の心をつかんだ元禄文化の人物は誰ですか?
⑲ 解答:近松門左衛門(ちかまつもんざえもん)
解説:義理と人情の世界を描き、庶民から絶大な人気を得ました。
⑳ 「見返り美人図」などで知られ、浮世絵の版画を完成させたとされる元禄文化の絵師は誰ですか?
⑳ 解答:菱川師宣(ひしかわもろのぶ)
解説:一枚の絵として独立した浮世絵版画を確立し、後の浮世絵発展の基礎を築きました。
ガチガチのルールで平和な世の中の土台を築いた江戸時代前半。
でも、この平和が、やがて新しい問題を生んでいくことになるんだ。それは、また次回!
😊「なんだ。簡単じゃん」と感じてもらえたらすごくうれしいです。わかりにくい問題があったら、教えてください。簡単に説明したり、わかりやすい他の方法で、もっと楽に理解が深まります。
「ブログより実際に話しがしたい」「もっといろいろ教えてほしい!」と感じた人は、無料体験や相談に来てください! この先生に相談をすることや習うことができます! 少し勇気を出して、ぜひ一度体験しに来てください! 「わかるって面白い」とか成績が良くなる自分を感じられる日がきます。お問い合わせ・ご質問はこちらです。




.jpg)
-1024x538.jpg)
-1024x538.jpg)
-1024x538.jpg)