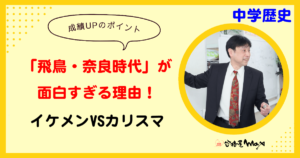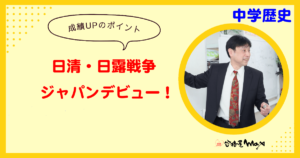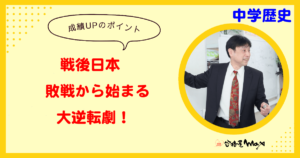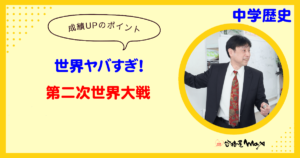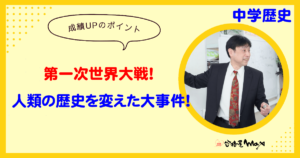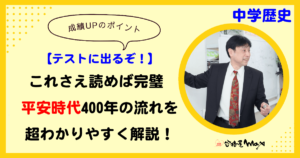1. 飛鳥時代 ~ヒーロー聖徳太子の大活躍!~
👦ゆうと:「あかり、飛鳥時代って人の名前も漢字もごちゃごちゃして、全然頭に入んないんだよ…」
👧あかり:「わかる~!でもストーリーで追えば、けっこう面白いんだよ。まずはこの時代のスター!聖徳太子の“神ワザ4連発”からいこう!」
- 冠位十二階
👧あかり:「『えらい人は家の生まれで決まる』って考えを壊して、『頑張った人をちゃんと評価するよ!』っていう仕組みを作ったの。」
👦ゆうと:「現代で言えば、テストの点とか努力でチャンスをつかめる感じだね!」 - 十七条の憲法
👧あかり:「役人たちがケンカばっかじゃ仕事にならないでしょ?だから“仲良く協力しよう”っていうルールを作ったんだよ。」
👦ゆうと:「『和を以て貴しとなす』ってやつか。今でも通じる考え方だな!」 - 遣隋使
👧あかり:「中国の“隋”っていう超大国に、小野妹子たちを派遣したんだよ。しかも“ウチら日本も対等っす!”って強気の手紙を持たせたんだ。」
👦ゆうと:「え、すごくない!?小国のくせに勇気ありすぎ!」 - 飛鳥文化
👧あかり:「仏教文化を広めて法隆寺を建てたのも太子!なんと今も残ってる世界最古の木造建築なんだって。」
👦ゆうと:「やばっ!1400年以上残ってるとかチートじゃん。」
2. 大化の改新と白村江の戦い
👦ゆうと:「でも聖徳太子のあとってどうなるの?」
👧あかり:「そこで出てくるのが“大化の改新”。645年、中大兄皇子と中臣鎌足が悪さしてた蘇我氏を倒したんだよ!」
👦ゆうと:「“むしごろし”で645!年号の語呂合わせ覚えやすい!」
- 公地公民
👧あかり:「土地も人も天皇のもの!っていうルールを決めたんだ。国づくりの土台になったんだよ。」
👦ゆうと:「でもその後、日本って負け戦あったんだっけ?」
👧あかり:「そう、“白村江の戦い”で唐と新羅にボロ負け…。日本中が『やばい、次は攻められるかも!』って大パニック。」
👦ゆうと:「それで防衛のために九州に太宰府を作ったんだね!」
3. 大宝律令で国の仕組みが完成!
👧あかり:「ピンチを乗り越えて、701年に“日本初の本格ルールブック”=大宝律令ができたんだ!」
👦ゆうと:「二官八省とか国司とか、今の政府の基礎みたいな仕組みが整ったんだね。」
4. 奈良時代 ~平城京と大仏のインパクト!~
👦ゆうと:「次は奈良時代か。何がすごいの?」
👧あかり:「まずは710年、“なんと立派な平城京”!って覚えてね。碁盤の目みたいに整った都だったんだよ。」
- 税の仕組み
👧あかり:「班田収授法で田んぼを貸すかわりに、農民は“租・庸・調”っていう税を納めたんだ。お米、布、特産物とかね。」
👦ゆうと:「それって農民めっちゃ大変じゃん…。」 - 墾田永年私財法(743年)
👧あかり:「新しく開いた土地は、持ち主のものにしていいよ!っていう法律。これで貴族やお寺が土地を広げて、“荘園”がどんどんできたんだ。」
👦ゆうと:「で、その荘園を守るために武装した人が“武士”の始まりになるんだね!」 - 奈良の大仏
👧あかり:「聖武天皇は、戦いや病気で不安な世の中を仏の力で守ろうとしたの。だから東大寺の大仏を造ったんだよ。」
👦ゆうと:「デカすぎ!しかも1300年前に作ったってヤバい。」
5. 今日のまとめ!
👦ゆうと:「飛鳥・奈良時代って、“天皇中心の国づくりプロジェクト”だったんだね!」
👧あかり:「そうそう!聖徳太子から始まって、大化の改新、大宝律令、平城京、奈良の大仏…って流れで、日本の基礎ができていったんだよ。」
👦ゆうと:「でも“墾田永年私財法”で荘園が広がって、“武士”が出てくる布石になったんだな。」
👧あかり:「歴史って、点じゃなくて線でつながってるから面白いんだよ!」
👦ゆうと:「よっしゃ!テスト対策もバッチリだな!」
【中学生のための爆わかり歴史ブログ】飛鳥・奈良時代を完全攻略!最強の国づくりストーリーをマスターしようぜ!
やっほー!歴史の授業、聞いてるだけで眠くなっちゃう…💤
「似たような名前と漢字ばっかりで、マジ無理…」ってなってるキミに朗報!
今日のテーマは、まるでマンガみたいなヒーローと大事件がいっぱいの「飛鳥・奈良時代」だよ!
テストに出まくるところだけど、ストーリーで覚えれば超カンタン!
この時代のテーマは、たった一つ!
【天皇を中心とした、最強の日本づくりプロジェクト!】
これさえ頭に入れておけば、全部つながって見えてくるから不思議だよ。さっそく行ってみよう!🚀
第1章 飛鳥時代 ~ヒーローとピンチの連続!~
国づくりスタート!スーパーヒーロー聖徳太子の「神ワザ4連発」✨
日本の国づくりプロジェクト、最初の主人公はこの人!聖徳太子!
彼がやった「神ワザ」は、テストに出る4点セットで覚えちゃおう!
- 冠位十二階(かんいじゅうにかい)
「家柄もいいけど、これからは実力っしょ!」っていう画期的なアイデア。頑張った人が評価される仕組みを作ったんだ。 - 十七条の憲法
「役人のみんな、チームとして最高の仕事をしようぜ!」っていうルールブック。「和を以て貴しとなす(みんなで仲良く話し合おう!)」って言葉は、1400年後の今でも大切にされてるんだ。すごいよね! - 遣隋使(けんずいし)の派遣
当時の最強国家・中国(隋)に、小野妹子たちを派遣!しかも「ウチら、対等な感じでよろしく!」っていう強気な手紙まで渡しちゃう大胆さ。 - 飛鳥文化
日本で最初の仏教文化をプロデュース!聖徳太子が建てた法隆寺は、なんと世界最古の木造建築として今も残るレジェンドなんだ!
激震!正義のクーデター「大化の改新」(645年)💥
聖徳太子がいなくなったら、蘇我(そが)氏っていう一族がやりたい放題に…😱
そこで立ち上がったのが、中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)と中臣鎌足(なかとみのかまたり)の最強コンビ!
- 「むし(645)をころして大化の改新!」で年号を覚えよう!
- 【超重要ワード】公地公民(こうちこうみん)
「この国の土地と人は、ぜーんぶ天皇(国)のものね!」と宣言!これが、これからの国づくりの土台になるんだ。
日本、大ピーンチ!「白村江の戦い」で国づくりのギアが上がる!🔥
仲良しだった朝鮮半島の国「百済」を助けに行った日本。でも、最強の「唐」と「新羅」の連合軍に、まさかのボロ負け…😭
「ヤバい、次はウチらが攻められるかも!?」
日本中がガチで焦ったんだ。この海外からの危機感が、天皇中心の国づくりをスピードアップさせる最大の理由になったんだよ!
九州に太宰府(だざいふ)っていう防衛基地を置いて、急いで国のルール作りを進めたんだ。
ついに完成!日本の公式ルールブック「大宝律令」(701年)📖
国のピンチを乗り越え、ついに国づくりの総仕上げ!
壬申の乱っていう後継者争いを勝ち抜いた天武天皇がリーダーシップを発揮して、701年、日本初の本格的な法律「大宝律令」が完成したんだ!
これで、国の仕組み(二官八省とか、地方を治める国司とか)がバッチリ決まって、聖徳太子が夢見た「天皇中心の中央集権国家」が出来上がったんだよ!
第2章 奈良時代 ~ピカピカの都とデカすぎる大仏!?~
「なんと(710)立派な平城京!」
ルールもできたし、次はイケてる都を作ろうぜ!ってことで、710年に平城京(今の奈良県)が完成!碁盤の目みたいなキレイな街だったんだ。
みんなの暮らしと、ちょっぴり重い税金の話…💦
- 班田収授法(はんでんしゅうじゅほう)
みんなに田んぼ(口分田)を貸してあげる制度。でも、その代わり… - 租・庸・調(そ・よう・ちょう)
お米や特産物を税として納める義務があったんだ。兵役もあったし、農民の負担は正直、超キツかった…。
【歴史が動いた!】墾田永年私財法と「武士」の誕生🌱
人口が増えて、みんなに配る田んぼが足りなくなってきた!そこで政府が出したとんでもない法律が…
墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいほう)
「自分で新しく開墾した土地は、ずーっとキミのものにしてOK!」
この法律が、日本の歴史を大きく動かす!
① お金持ちの貴族やお寺が、人を雇ってガンガン土地を広げる
② 荘園(しょうえん)っていう、巨大なプライベートな土地が生まれる
③ 「オレたちの荘園は、オレたちで守る!」と武装する人たちが登場…
そう、これが次の時代に大活躍する「武士」の誕生につながっていくんだ!
聖武天皇と奈良の大仏🙏
当時の日本は、争いや病気の流行で社会が不安定だったんだ。
そこで聖武天皇は「仏様のパワーで、平和な国を!」と願い、全国に国分寺を建設。
そして都の奈良には…みんなも知ってる、あの東大寺の大仏を造ったんだ!スケールがでかすぎる!
この時代の国際色豊かな文化を天平文化っていうよ。
今日のまとめ!
- 飛鳥・奈良時代は、ヒーローたちが海外からのピンチを乗り越えて「天皇中心の国」の土台を作った、アツい時代だった!
- でも、墾田永年私財法っていう新しいルールがきっかけで「荘園」が生まれ、それが「武士」の登場につながっていくんだ。
歴史って、一つの出来事が次の時代の扉を開けるカギになってて、本当につながってて面白いよね!
今回の内容はテストの頻出ポイントだから、しっかり復習しておこう!
それじゃ、また次の記事で会おうね!勉強がんばれ!👍
【飛鳥・奈良時代】実力診断!確認問題20
① 家柄にとらわれず、才能や功績のある人物を役人とするために聖徳太子が定めた制度は何ですか?
① 冠位十二階(かんいじゅうにかい)
解説:聖徳太子が行った国づくりの一つです。役人を12の位に分け、冠の色で区別しました。
② 聖徳太子が定めた役人の心構えで、「和を以て貴しとなす」の一文が有名なものは何ですか?
② 十七条の憲法
解説:これも聖徳太子が定めたもので、役人としての心構えを示したものです。
③ 聖徳太子が隋(中国)の進んだ制度や文化を学ぶために派遣した使節を何といいますか?
③ 遣隋使(けんずいし)
解説:代表的な人物は小野妹子です。隋の進んだ文化や政治制度を日本に取り入れる目的がありました。
④ 645年、中大兄皇子と中臣鎌足が蘇我氏を倒して始めた、天皇中心の国づくりを目指す改革を何といいますか?
④ 大化の改純
解説:「むしごろし(645)の大化の改新」で年号も覚えましょう。ここから元号(年号)が使われ始めました。
⑤ 大化の改新で示された、全国の土地と人民はすべて天皇(国家)のものであるとする基本方針を何といいますか?
⑤ 公地公民(こうちこうみん)
解説:この後の班田収授法など、国の土地制度の基本となる考え方です。
⑥ 日本が、同盟国であった百済を救うために出兵し、唐と新羅の連合軍に大敗した戦いは何ですか?
⑥ 白村江(はくすきのえ /はくそんこう)の戦い
解説:この敗北による危機感が、日本の律令国家建設を急がせる大きなきっかけとなりました。
⑦ ⑥の敗戦後、唐や新羅の来襲に備えて九州の防衛拠点として置かれた役所の名前は何ですか?
⑦ 太宰府(だざいふ)
解説:太宰府には、東国から徴兵された防人(さきもり)が配置され、国防の最前線となりました。
⑧ 701年に完成した、日本で最初の本格的な法律(律と令)は何ですか?
⑧ 大宝律令(たいほうりつりょう)
解説:「律」は刑罰のルール、「令」は政治の仕組みのルールです。この完成で中央集権国家の仕組みが整いました。
⑨ 大宝律令で定められた中央の政治の仕組みで、神祇官と太政官、そしてその下の八省からなる制度を何といいいますか?
⑨ 二官八省(にかんはっしょう)
解説:神祇官(神様ごと)と太政官(政治)の二官と、その下に実務を行う八省が置かれました。
⑩ 地方の「国」を治めるために、都から派遣された役人(貴族)を何といいますか?
⑩ 国司(こくし)
解説:中央集権の象徴で、中央から派遣されました。ちなみに、その土地の有力者が任命されたのは「郡司(ぐんじ)」です。
⑪ 710年、唐の都「長安」にならって奈良につくられた都の名前は何ですか?
⑪ 平城京(へいじょうきょう)
解説:「なんと(710)立派な平城京」の語呂合わせで覚えましょう。
⑫ 奈良時代、戸籍に基づいて6歳以上の男女に田んぼ(口分田)を与え、その人が死ぬと国に返させる制度を何といいますか?
⑫ 班田収授法(はんでんしゅうじゅほう)
解説:公地公民の原則に基づいた土地制度です。戸籍が6年ごとにつくられたこともポイントです。
⑬ 農民が税として納めた「租・庸・調」のうち、「租」とは何を納める税ですか?
⑬ 収穫した稲(の約3%)
解説:「庸」は労役か布、「調」は地方の特産物です。区別して覚えましょう。
⑭ 奈良時代、人口が増えて口分田が不足したため、743年に政府が出した、新しく開墾した土地の永久私有を認める法律は何ですか?
⑭ 墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいほう)
解説:この法律が、公地公民の原則を崩していくきっかけとなる、歴史の大きな転換点です。
⑮ ⑭の法律が出された結果、貴族や寺社が拡大させた私有地のことを何といいますか?
⑮ 荘園(しょうえん)
解説:貴族や寺社は、この荘園からの収入でさらに豊かになっていきました。
⑯ 荘園の発生は、武士が生まれるきっかけとなりました。それはなぜですか。「守る」という言葉を使って簡潔に説明しなさい。
⑯ (例)自分たちの荘園を、他の豪族や役人から守るために武装したから。解説:荘園という「私有財産」が生まれたことで、それを自分たちの力で「守る」必要が出てきたのが武士の起源です。
⑰ 仏教の力で国家の不安をしずめようと考え、奈良に東大寺と大仏を造るよう命じた天皇は誰ですか?
⑰ 聖武天皇(しょうむてんのう)
解説:当時は疫病の流行や貴族の反乱など、社会が不安定だったため、仏教の力に頼ろうとしました。
⑱ 聖武天皇の命令により、全国各地に建てられた寺院(男性僧侶の寺)を何といいますか?
⑱ 国分寺(こくぶんじ)
解説:女性の僧侶(尼)のための国分尼寺(こくぶんにじ)もセットで建てられました。
⑲ 奈良時代に栄えた、聖武天皇の時代の年号がつけられた、国際色豊かな仏教文化を何といいますか?
⑲ 天平文化(てんぴょうぶんか)
解説:東大寺の正倉院に残る宝物が、その国際性を物語っています
⑳ 天皇による支配の正当性を示すために奈良時代に編纂された、現存する日本最古の歴史書を2つ答えなさい。
⑳ 古事記、日本書紀
解説:どちらも神話から始まる歴史が書かれており、天皇の支配の由来を明らかにしようとしました。
😊「なんだ。簡単じゃん」と感じてもらえたらすごくうれしいです。わかりにくい問題があったら、教えてください。簡単に説明したり、わかりやすい他の方法で、もっと楽に理解が深まります。
「ブログより実際に話しがしたい」「もっといろいろ教えてほしい!」と感じた人は、無料体験や相談に来てください! この先生に相談をすることや習うことができます! 少し勇気を出して、ぜひ一度体験しに来てください! 「わかるって面白い」とか成績が良くなる自分を感じられる日がきます。お問い合わせ・ご質問はこちらです。