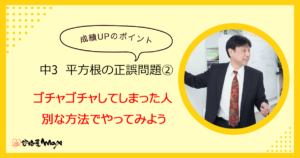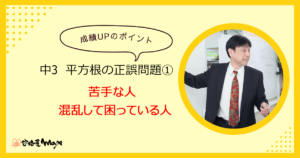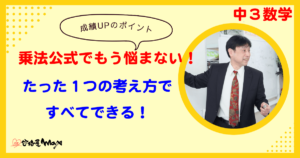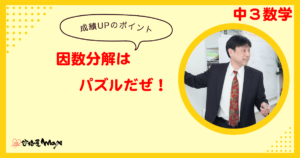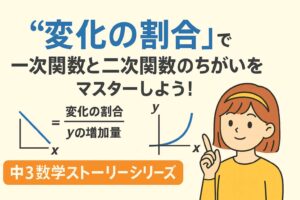💬 ゆうと&あかりのストーリー解説 応用編
二次関数 応用編「変化の割合を使った問題に挑戦!」
🧩 問題1 変化の割合の公式を使ってaを求める。
関数 y=2x² で、xの値が a から a+2 まで増加するとき、
変化の割合が 16 になりました。
このときの a の値 を求めましょう。
👦 ゆうと:「“変化の割合”って、また出た…。これって傾きと同じ考え方だったよね?」
👧 あかり:「そうそう! 二次関数では“区間ごとの傾き”ってイメージ。
公式は――」
\( \text{変化の割合} = \frac{\text{yの増加量}}{\text{xの増加量}} \)
👦 ゆうと:「じゃあ、まずxとyの対応表を作って、どう変わるか見てみよう。上がx、下がyだよ。」
| x | a | a+2 |
| y | 2a² | 2(a+2)² |
👧 あかり:「xの増加量は (a+2) − a = 2 ね。」
👦 ゆうと:「OK。じゃあ次、yの増加量は…
2(a+2)² − 2a²。ちょっと展開してみよう。」
yの増加量
=2(a²+4a+4) − 2a²
= 2a²+8a+8 − 2a²
= 8a+8
👧 あかり:「ここで“a²”の項が消えるから安心!
二次関数の“変化の割合”は、aの式になるんだね。」
👦 ゆうと:「ということは、変化の割合は――」
\( \text{変化の割合} = \frac{\text{yの増加量}}{\text{xの増加量}} \) =\( \frac{8a+8}{2} \)=4a+4
👧 あかり:「この“4a+4”が、aからa+2の区間の変化の割合ね。」
👦 ゆうと:「なるほど。で、問題文では変化の割合が16だから――」
4a+4=16
⇒ 4a=12
⇒ a=3
👧 あかり:「正解!✨ a=3のとき、変化の割合が16になるんだね。」
👦 ゆうと:「なんだかスッキリ!
“区間ごとに傾きが変わる”っていうのが、やっとわかってきた!」
🧮 問題2 二次関数と一次関数の変化の割合が等しい時のaを求める
関数 y=ax² と y=−5x+6 で、xが 4から6まで 増加するとき、
変化の割合が同じになりました。
このときの a の値 を求めましょう。
👦 ゆうと:「今度は2つの関数!?ちょっと複雑そう…。」
👧 あかり:「大丈夫。1つ1つ見ていこう。
一次関数 y=−5x+6 の変化の割合は、“傾き”と同じで常に −5。」
👦 ゆうと:「ふむふむ。じゃあ、二次関数 y=ax² のほうを計算してみよう。」
| x | 4 | 6 |
| y | 16a | 36a |
👧 あかり:「xの増加量は6−4=2、yの増加量は36a−16a=20a。」
👦 ゆうと:「だから変化の割合は――」
\( \text{変化の割合} = \frac{\text{yの増加量}}{\text{xの増加量}} \) =\( \frac{20a}{2} \)=10a
👧 あかり:「いいね。
で、『変化の割合が同じ』だから、10a=−5。」
👦 ゆうと:「えっと、両辺を10で割ると――」
\( a = -\frac{1}{2} \)
👧 あかり:「その通り!✨
\( a = -\frac{1}{2} \)のとき、二次関数の“区間の傾き”が一次関数の傾きと一致するんだ。」👦 ゆうと:「なるほど〜! 二次関数も、区間を切り取ると“その部分だけの傾き”が出るってことか!」
👧 あかり:「そういうこと! これが“平均の傾き”=変化の割合の考え方だよ。」
❓Q&Aコーナー:中3数学 変化の割合をスッキリ理解!
- Q1:👦 ゆうと:「二次関数の“変化の割合”って、どうして場所によって違うの?」
-
👧 あかり:「いい質問! 二次関数のグラフは“カーブ”してるでしょ?
だから、区間によってグラフの傾き(上がるスピードや下がるスピード)が変わるの。
つまり“変化の割合”は、カーブの形に合わせて変わるんだよ。」👦 ゆうと:「なるほど! 直線ならいつも同じだけど、放物線はカーブだから変わるんだね!」
- Q2:👦 ゆうと:「じゃあ、変化の割合って、どんな意味があるの?」
-
👧 あかり:「“平均の傾き”って考えるとわかりやすいよ。
たとえば x が 3 から 5 に変わる間に、y がどれだけ増えたかを割合で見てるの。
だから『この区間ではどれくらいの速さで上がった(下がった)か』を表してるんだね。」👦 ゆうと:「速さの平均、みたいな感じか!グラフの動き方を数字で表してるんだ!」
- Q3:👦 ゆうと:「計算で“a²の項が消える”って、どうしてそうなるの?」
-
👧 あかり:「そこが二次関数の面白いところ!
増加の差(yの増加量)をとると、同じa²どうしが引き算で消えるの。
残るのは“a”を含む一次の部分。
つまり、“変化の割合”ではaが主役になるんだね。」👦 ゆうと:「ほんとだ、展開して引いたらa²がなくなってた!
だから毎回“aが残る形”になるんだね。」 - Q4:👦 ゆうと:「一次関数と比べると、どこがいちばん違うの?」
-
👧 あかり:「一次関数は“傾き=変化の割合”が常に同じ。
でも二次関数は“xの場所ごとに変わる”の。
だから、一定じゃないっていうのが大きなちがいだね。」👦 ゆうと:「同じ公式を使っても、結果が変わるのはそのせいか!」
- Q5:👦 ゆうと:「変化の割合を求めるとき、間違いやすいポイントってある?」
-
👧 あかり:「あるある! いちばん多いのは、“yの増加量とxの増加量を逆にする”ミス。
あと、yの計算でa²が消えるのを見逃して“式が長くなる”パターンも多いよ。
対応表を見ながら、順番に整理するとミスが減るよ!」👦 ゆうと:「やっぱり“対応表”が大事なんだね!ちゃんと書くようにするよ!」
✅ ① 変化の割合の公式はこれ!
\( \text{変化の割合} = \frac{\text{yの増加量}}{\text{xの増加量}} \)この公式は 一次関数でも二次関数でも共通!
ただし、二次関数では区間によって値が変わることを忘れないで!
✅ ② 一次関数とのちがいを整理!
| 一次関数 | 二次関数 | |
|---|---|---|
| 変化の割合 | どこでも同じ(=傾きa) | 区間ごとに変わる |
| グラフの形 | 直線 | 放物線 |
| 計算の手順 | 傾きaをみればわかる | 区間ごとに計算が必要 |
✅ ③ 計算は「対応表」で整理!
どんな問題でも、まず対応表を作る。
| x | ○ | □ |
| y | ● | ■ |
順番を間違えない・式をきれいに整理できる、これだけでミスが激減!
✅ ④ “何を比べているのか”を意識!
\( \text{変化の割合} = \frac{\text{yの増加量}}{\text{xの増加量}} \)つまり、
「この区間ではどのくらい上がった(または下がった)のか?」
を数で表している。
式に振り回されず、グラフの動きをイメージすることが理解の近道!
🎯 先生からひとこと
二次関数の応用問題では、変化の割合の理解がカギになります。
公式を覚えるだけじゃなく、
「どうしてこうなるの?」を一度自分の言葉で説明できるようにしてみよう!
それができたら、この単元はもう完璧です!
🧮 🧮 二次関数 応用演習「変化の割合」まとめテスト(10題)
① 関数 y=x² について、xの値が a から a+3 まで増加するとき、
変化の割合が 10 であった。a の値を求めよ。
解答:
xの増加量=3
yの増加量=(a+3)² − a² = a²+6a+9 − a² = 6a+9
したがって
2a+3=10
→ 2a=72a=72a=7
→ a=3.5
② 関数y = a x² と y=−4x+8 の変化の割合が、xが 2 から 4 まで増加するときに等しい。
a の値を求めよ。
解答:
一次関数の変化の割合=−4
③ 関数 y = 3x² と y=ax+5 について、xが 1 から 3 まで増加するときの変化の割合が等しいとき、a を求めよ。
解答:
一次関数の変化の割合=a よって a=12
④ 関数y = 2x² について、xが a から a+2 まで増加するときの変化の割合が 10 のとき、a の値を求めよ。
解答:
変化の割合が 10 だから、4a+4=10 よって \( a = \frac{3}{2} \)
⑤ 関数y = a x² と y = 3x − 9 の変化の割合が、xが −2 から 0 まで増加するときに等しい。a の値を求めよ。
\( \text{二次関数の変化の割合} = \frac{\text{yの増加量}}{\text{xの増加量}} \)= \( \frac{0-4a}{2} \)= \( \frac{4a}{2} \)=-2a
2つの関数の変化の割合が等しいから、-2a=3 よって a=-1.5
⑥ 関数 y = 2x² について、xの値が a から a+3 まで増加するとき、
変化の割合が 22 であった。a の値を求めよ。
解答:
xの増加量=3
yの増加量=2(a+3)² − 2a²
=2(a²+6a+9) − 2a²=12a+18
変化の割合が22だから、4a+6=22 よって a=4
⑦ 関数y = 3x² について、xの値が a から a+3 まで増加するときの変化の割合を求めよ。
解答:
xの増加量=3
yの増加量=3(a+3)² − 3a²
=3(a²+6a+9) − 3a²=18a+27
変化の割合は、6a+9
⑧ 関数y = a x² と y = −5x+6 の変化の割合が、xが 4 から 6 まで増加するときに等しい。a の値を求めよ。
\( \text{二次関数の変化の割合} = \frac{\text{yの増加量}}{\text{xの増加量}} \)= \( \frac{36a-16a}{2} \)= \( \frac{20a}{2} \)=10a
2つの関数の変化の割合が等しいから、10a=-5 よって \( a = -\frac{1}{2} \)
⑨ 関数 y = 4x² について、xの値が a から a+3 まで増加するときの変化の割合が 20 のとき、a の値を求めよ。
解答:
\( \text{二次関数の変化の割合} = \frac{\text{yの増加量}}{\text{xの増加量}} \)= \( \frac{(4a²+24a+36)-4a²}{3} \)= \( \frac{24a+36}{3} \)=8a+12変化の割合が等しいから、8a+12=20 よって a=1
⑩ 関数 y = a x² と y = 2x − 10 について、xが 1 から 4 まで増加するときの変化の割合が等しい。a を求めよ。
解答:
\( \text{二次関数の変化の割合} = \frac{\text{yの増加量}}{\text{xの増加量}} \)= \( \frac{16a-a}{3} \)= \( \frac{15a}{3} \)=5a
2つの関数の変化の割合が等しいから、5a=2 よって \( a = \frac{5}{2} \)
📘 「止まって見える時間も、君はちゃんと進んでる」
どんなに頑張っても、すぐに結果が出ないときがあります。
でもそれは、「進んでいない」のではなく、「変化の途中」なんです。
二次関数のグラフみたいに、最初はゆるやかでも、
少しずつ傾きが変わって、やがてぐんと上がっていく瞬間がきます。
「変化の割合」を求めるたびに、
自分の努力にも“変化の割合”があることを思い出してください。
焦らず、比べず、
昨日の自分より、ほんの少しでも前に進めたらそれでOK。
👧 あかり:「変化を感じられないときこそ、実は内部で爆発力を一番ためているときなんだよ。」
👦 ゆうと:「二次関数の上昇カーブになりたい。頑張るぞ!」
今日も一歩、君の“上昇カーブ”を信じて進もう。
努力の線は、きっと未来で大きく上に伸びていくから。