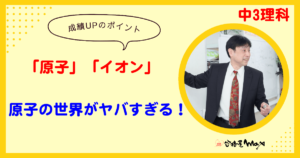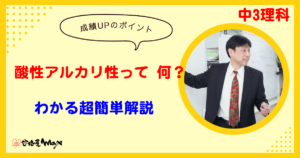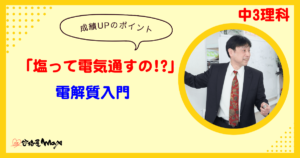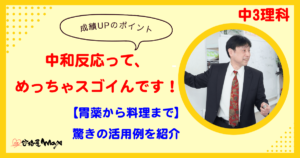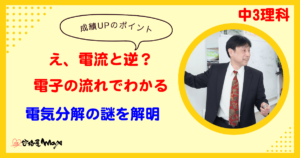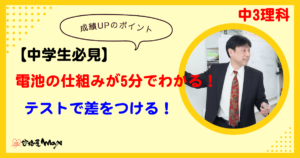📚 このブログは 「中3理科ストーリーシリーズ|定期テストも入試も安心」 の1本です。 会話形式で楽しく学べるので、理解が進み、テスト対策にも入試対策にも役立ちます。
👦 ゆうと(理科:苦手)
👧 あかり(理科:得意)
1. 基本用語をおさえよう
👦「ねぇ、遺伝って聞くと、なんか難しそう…。もう頭が痛いんだけど。」
👧「大丈夫!少しずついこう。まず“形質(けいしつ)”っていうのは、生き物の特徴のことだよ。」
👦「特徴?たとえば?」
👧「人間なら一重まぶたとか二重まぶた、エンドウ豆なら“丸い種子”とか“しわの種子”!」
👦「あっ、それなら分かる!」
👧「でね、その形質を決める“設計図”みたいなのが“遺伝子”。遺伝子は染色体の上に乗ってるの。」
👦「ふむふむ、なんとなくイメージできるぞ!」
2. 交配ってどういうこと?
👦「ところで、“交配する”って教科書に書いてあるけど、どういう意味?」
👧「交配っていうのは、オスとメスを組み合わせて子どもを作ること。植物なら“おしべの花粉”を“めしべ”につけて受粉させることだよ。」
👦「あ、それって自然に起こるんじゃないの?」
👧「そうそう。エンドウ豆は放っておくと、自分の花の中だけで受粉しちゃう。“自家受粉”って言うんだ。」
👦「自家受粉?」
👧「同じ花の中で“おしべの花粉”が“めしべ”について子どもができること。だから普通はわざわざ他の株と交わらなくても、種ができちゃうんだよ。」
👦「なるほど。でも、メンデルは“掛け合わせる実験”をしたんだよね?」
👧「そう!メンデルは自家受粉をわざと止めて、別の株どうしで交配させたの。これを“他家受粉”っていうんだ。自然のままじゃ起きにくいから、メンデルの手でおしべの花粉をめしべにつけて実験したんだよ。」
👦「へぇ!だからちゃんと結果をコントロールできたんだね!」
3. 純系ってなに?
👦「“純系”って言葉も出てきた!」
👧「純系っていうのは、何世代も同じ特徴が続いているグループのこと。例えば丸い豆だけをずっと育てていくと、子や孫も丸い豆しかできない。このグループを“丸の純系”って言うんだよ。」
👦「なるほど、じゃあ“しわの純系”もあるんだ!」
👧「そうそう。そして“純系どうしを掛け合わせたらどうなるか?”っていうのがメンデルの実験なんだ。」
4. 遺伝子の書き方ルール
👦「ねぇ、“丸の純系はAA”とか“しわの純系はaa”とか書いてあるけど、これって何?」
👧「いい質問!この書き方は遺伝子を表すルールなんだよ。大文字の“A”は“強い形質(顕性形質)=丸”を表す。小文字の“a”は“弱い形質(潜性形質)=しわ”を表すんだ。」
👦「へぇ!じゃあAAは“強い丸が2つ”ってこと?」
👧「そう!AAだと丸、aaだとしわ。Aaみたいに両方混じっていると、強い方=Aの丸が現れるんだよ。」
👦「なるほど!ルールがわかった!」
5. メンデルの実験①:純系同士を掛け合わせると?
👧「丸の純系(AA)と、しわの純系(aa)を交配させると…」
👦「子どもはどうなるの?」
👧「全部“Aa”になって、形はぜんぶ丸になるの!」
👦「えっ?しわはゼロなの?」
👧「そう。A(丸)の方が強いから、a(しわ)を持っていても丸になるんだ。」
👉 これを 顕性の法則 っていうんだ。
| A(精子) | A(精子) | |
|---|---|---|
| a(卵) | Aa(丸) | Aa(丸) |
| a(卵) | Aa(丸) | Aa(丸) |
6. メンデルの実験②:子どもどうしを掛け合わせると?
👦「じゃあ、親から生まれた子どもの“丸(Aa)”どうしを掛け合わせたらどうなるの?」
👧「ここがポイント!まず、Aaっていう子どもが生殖細胞(卵や精子)を作るとき、“分離の法則”が働くんだよ。」
👦「分離の法則って?」
👧「減数分裂で、遺伝子にが2つに別れて、それぞれ別の生殖細胞に入ること。だから、Aaからは“Aを持つ生殖細胞”と“aを持つ生殖細胞”ができるんだ。」
👦「なるほど!じゃあ、卵と精子でAとaがいろいろ組み合わさるのか!」
👧「そういうこと!表にするとこうなるよ。」
| A(精子) | a(精子) | |
|---|---|---|
| A(卵) | AA(丸) | Aa(丸) |
| a(卵) | Aa(丸) | aa(しわ) |
👧「結果は、AA(丸)、Aa(丸)、Aa(丸)、aa(しわ)。」
👦「丸が3つで、しわが1つ! あ~ なるほどね。」
👧「そう!3:1の割合になるんだね。」
7. 顕性と潜性って?
👦「ところで“強い”“弱い”って言ってたけど?」
👧「あ、本当は、“強い方”を顕性(けんせい)形質、“弱い方”を潜性(せんせい)形質って言うんだよ。」
👦「丸が顕性、しわが潜性ってことね!」
👧「その通り! 純系をかけあわせたときに、子に出る形質がを顕性(けんせい)形質。 出たがりの性質と思えておけばいいよ」
8. 会話で確認テスト!
👧「最後にチェックしてみよっか。いくよ!」
👧「“形質”って何のこと?」
👦「生き物の特徴!例えばエンドウ豆の丸とかしわ!」
👧「じゃあ“遺伝子”は何?」
👦「形質を決める設計図で、染色体の上にある!」
👧「AAとaaをかけ合わせたら、子はどうなる?」
👦「全部Aaで、形は丸!」
👧「親から生まれた子どものAaどうしをかけ合わせたときの形質の比率は?」
👦「丸が3、しわが1!つまり3:1!」
👧「“強い方の形質が出る”ことを何の法則っていう?」
👦「顕性の法則!」
👧「遺伝子が減数分裂で別々の生殖細胞に分かれる法則を何というか?」
👦「分離の法則!」
👧「完璧!これが言えれば入試もバッチリだね!」
👦「やったー!自信ついた!」
- 形質は遺伝子によって決まる。
- 顕性(けんせい)と潜性(せんせい)があり、顕性の形質が表に出やすい。
- 減数分裂のとき、対になっている遺伝子は別々の生殖細胞に分かれる(分離の法則)。
- 子どもの遺伝子の組み合わせは、できた生殖細胞(2つ)を表の縦に2つ、横に2つ入れて、マス目の中に組み合わせを書き込むことで分かる。
- その結果として、丸:しわの形質が 3:1の比率で現れる。
| A(精子) | a(精子) | |
|---|---|---|
| A(卵) | AA(丸) | Aa(丸) |
| a(卵) | Aa(丸) | aa(しわ) |
👉 ポイントは「ただ3対1を覚えるのではなく、表を書いて考える」こと!これが理解のカギだよ。
「親に似る/似ない」っていう遺伝のしくみ
実は授業だけでなく身近な生活の中でも感じられるんです。 家族で楽しめる“遺伝のふしぎ”を紹介した
記事はこちら 👉