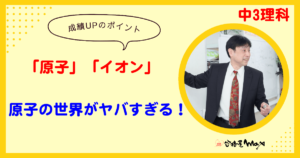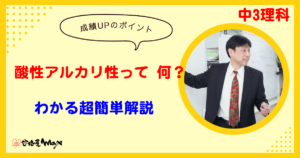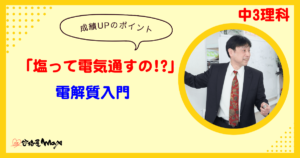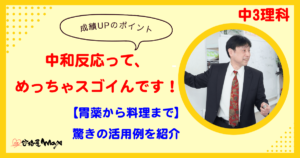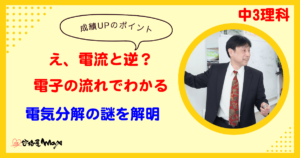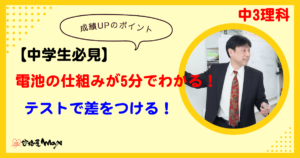急ブレーキや「壁を押す」など身近な例と図でスッと理解。
「力のつり合い」との違い/一問一答/テストに出るポイント付き。
🪄導入:急ブレーキのとき、前につんのめるのはなぜ?
👦 ゆうと:「この前、バスが急に止まったとき、体が前に“グラッ”て倒れたんだよ。
あれ、なんでなんだろう?」
👧 あかり:「いいところに気づいたね!
実はそれ、“慣性の法則”が働いているんだよ。今日はこの“慣性(かんせい)”と“作用・反作用”をセットで理解しよう!」
① 慣性の法則ってどんな法則?
👧 あかり:「“慣性の法則”を簡単に言うとね——
『物体は、力を受けないかぎり、今の状態を続けようとする』 という法則だよ。」
👦 ゆうと:「つまり、“止まってるものは止まったまま”“動いてるものは動きつづける”ってこと?」
👧 あかり:「そうそう!それが“慣性”という性質なんだ。
ガリレオやニュートンも、この法則をもとに運動の基本を考えたんだよ。」
🔍図解で確認!
┌───────────────┐
│ 力がはたらかないとき(摩擦なし) │
└───────────────┘
▶︎▶︎▶︎▶︎ ● ▶︎▶︎▶︎▶︎ → 一定の速さで動き続ける
🧠 ポイント
- 力が加わらないと、動きは変わらない。
- 止まっているものは止まったまま。
- 動いているものは、等速直線運動する。
② 身の回りの「慣性の法則」例
👧 あかり:「“慣性”は実は身近にたくさんあるよ。」
- 🚗 車が急ブレーキをかけたとき → 体が前につんのめる(体が動こうとする)
- 🧤 手のホコリを払うとき → 手を急に止めると、ホコリだけ飛んでいく(ホコリが動き続けようとする)
- ⚽ サッカーボールが転がり続けるのは? → 摩擦という「止める力」が弱いから。
👦 ゆうと:「なるほど、どれも“動こうとする”“止まろうとする”ってことか!」
👧 あかり:「そう。ちなみに、質量が大きいほど慣性も大きいんだよ。
だから重いものほど止めるのが大変!」
③ 力はペアで働く!「作用・反作用の法則」
👧 あかり:「次は“作用・反作用の法則”。
これも中間・期末テストに出やすい重要ポイント!」
👦 ゆうと:「名前は知ってるけど…正直よくわかんない。」
👧 あかり:「これはね、力はいつもペアで働くという法則。
つまり、“押したら押し返される”!」
🔍図解で理解!
Aさん →(押す) 壁
↑ ↓
←(押し返す)
👧 あかり:「Aさんが壁を20Nの力で押したら、壁もAさんを20Nの力で押し返すんだよ。
この2つの力は——」
🧩 作用と反作用の関係
- 大きさ:同じ
- 向き:反対
- 一直線上:同じ線上にある
- 働く場所:別の物体どうし
④ 「力のつり合い」との違い
👦 ゆうと:「それって、“力のつり合い”のときも同じじゃない?」
👧 あかり:「そこがテストでよく間違えるところ!
まとめるとこう👇」
| 比較項目 | 力のつり合い | 作用・反作用 |
|---|---|---|
| はたらく物体 | 1つの物体の中 | 2つの物体の間 |
| 力の関係 | 同じ大きさ・反対向き | 同じ大きさ・反対向き |
| 例 | 机の上の本 | 壁を押すAさんと壁 |
👧 あかり:「“1つの物体に働く”のが力のつり合い、
“2つの物体どうしで働く”のが作用・反作用。ここをしっかり区別しよう!」
⑤ 例題で確認!
🧮 例題1
Aさんが壁を20Nの力で押しています。
このとき壁はAさんにどんな力を加えていますか?
【解答】
壁はAさんに、同じ大きさ(20N)で反対向きの力を加える。
🧮 例題2
車が急に止まると、体が前に投げ出されそうになるのはなぜですか?
【解答】
体が動きつづけようとする慣性をもっているから
⑥ 一問一答で確認しよう!
① 慣性の法則とは?
物体は力を受けないかぎり今の状態を続けようとする性質
② 質量が大きいほど慣性はどうなる?
大きくなる。
③ 作用・反作用の関係とは?
2つの物体に、大きさが同じで向きが反対の力がはたらく。
④ 力のつり合いと作用・反作用の違いは?
1つの物体か2つの物体かの違い。
⑤ 作用・反作用の例を1つ挙げよ。
| 壁を押すと壁から押し返される。 |
💡慣性と作用・反作用を本質から理解するQ&A
- Q1. 👦「止まっている物体は“止まろうとしている”のか?」
-
👧 あかり:「実は物体は“止まろうとしている”わけじゃないんだよ。」
👦 ゆうと:「え?でも、だんだんに止まるじゃん?」
👧 あかり:「それは摩擦や空気抵抗などの“止まる力”が働いているから。
もし摩擦や空気抵抗がゼロなら、止まらずにずっと動きつづけるの。
だから“止まる”のは力を受けた結果であって、止まろうとしてるわけじゃない。」👦 ゆうと:「なるほど…“慣性”って、“今の状態を変えない”って意味なんだね!」
- Q2. 👦「“慣性が大きい”って、どういうこと?」
-
👧 あかり:「それは“動きにくくて止まりにくい”ってこと!」
👦 ゆうと:「動きにくいのに止まりにくいって、なんか矛盾してる気がする…。」
👧 あかり:「たとえば大型トラック。
動き出すのに力がいるけど、いったん動くと止めるのも大変。
これが“質量が大きい=慣性が大きい”ということなの。
つまり“変化しにくい”ってこと!」👦 ゆうと:「あー、“変わりたくない”って感じなんだね。まるで日曜の朝の僕みたい…!」
👧 あかり:「(笑)まさに“現状維持の力”が強いってことだね!」
- Q3. 👦「壁を押しても動かないのに、なんで“力”があるって言えるの?」
-
👧 あかり:「いい質問だね!“動かない”=“力がない”じゃないの。」
👦 ゆうと:「え?でも押してるのに、壁がびくともしないよ?」
👧 あかり:「壁が“押し返してる”からだよ。
ゆうとが20Nで押したら、壁も20Nで押し返す。
だから見た目は動かないけど、力のやりとりは確かに起きてるの。
これが“作用・反作用”の関係!」👦 ゆうと:「なるほど、見えないけどちゃんと力が存在してるんだね。」
- Q4. 👦「作用・反作用って、どっちが“先”に起こるの?」
-
👧 あかり:「どっちも同時に起こるんだよ!」
👦 ゆうと:「同時!? じゃあ“押す”前に“押し返される”ことはないの?」
👧 あかり:「そう。力はペアで生まれるの。
“押す”と同時に“押し返す”が発生してる。
だから片方だけが先、ってことはないの。
これが“対になって存在する”という物理の大原則!」👦 ゆうと:「まるで息を吸うときに吐く空気が同時にあるみたいな関係だね。」
👧 あかり:「うまいこと言うね!それくらい、切り離せない関係なんだ。」
- Q5. 👦「力がつり合ってるときと、作用・反作用のとき。どっちの方が“強い力”なの?」
-
👧 あかり:「“強さ”はどちらも同じ。でも、働く相手がちがうの。」
👦 ゆうと:「うーん…イメージが難しい。」
👧 あかり:「たとえば机の上の本を考えてみよう。
重力(地球から本にはたらく力)と、机の垂直抗力(机から本にはたらく力)がつり合ってる。
これは“力のつり合い”。」<どちらも本に力がはたらいている>👧 あかり:「一方で、“本が机を押す力”と“机が本を押し返す力”は、<本から机にはたらく力>と
<机から本にはたらく力>で、別の物体間で起きてる。それが“作用・反作用”だよ。
つまり、“どっちが強いか”じゃなく、“どこに働くか”が大事なんだ!」👦 ゆうと:「そっか。“力のつり合い”と“作用・反作用”は別の世界の話なんだね!」
👧 あかり:「その通り!そこを理解できたら、もう物理の基礎はバッチリ!」
🎯先生のこれだけは押さえろ!+テストにはここが出る!
🧠 これだけは押さえろ!
① 慣性の法則
物体は、力が加わらない限り「今の動きを変えない」。
静止してれば静止したまま、動いていれば、等速直線運動をする。
② 慣性の大きさ=質量の大きさ
質量が大きいほど、動きにくく止まりにくい。
トラックが止まりにくいのも、このため!
③ 作用・反作用の法則
力は必ずペアで存在!
押すと同時に押し返される。
「力のキャッチボール」が自然界では常に起きている。
④ 力のつり合いとの違い
「力のつり合い」は1つの物体に働く力。
「作用・反作用」は2つの物体の間に働く力。
同じ“大きさ・反対向き”でも、相手が違う!
⑤ “動かない”=“力がない”ではない
動かないのは、力がつり合っているから。
力そのものはしっかり存在している!
🧩 テストにはここが出る!(具体的出題例つき)
【出る①】定義を正確に説明する問題
Q1 「慣性の法則」とはどのような法則か。簡潔に説明しなさい。
模範解答
物体は、外から力を受けないかぎり、静止していれば静止したまま、動いていれば、等速直線運動をしようとする性質。
出題意図
→ 用語をただ暗記しているかではなく、「状態を変えない性質」という本質表現を使えるかを確認。
【出る②】日常現象を“法則”で説明する問題
Q2 車が急に止まったとき、乗っている人の体が前に倒れそうになるのはなぜか。
(ヒント:ある法則を使って説明する)
模範解答
人の体が、動いたままでいようとする慣性の性質をもっているから。
出題意図
→ 「慣性」という語を使って説明できるかがポイント。
→ 「体が前に倒れるから」だけでは×。
【出る③】図を使って“力の関係”を説明する問題
Q3 図のように、人が壁を押しているとき、
A)どんな力がはたらいているか。
B)「作用・反作用の法則」を使って説明しなさい。
模範解答
A)人が壁を押す力と、壁が人を押し返す力がはたらいている。
B)これら2つの力は大きさが同じで、向きが反対の力(作用・反作用)である。
出題意図
→ 図中の矢印を正しく描けるか、2つの物体を意識できているかを確認。
【出る④】「力のつり合い」との区別を問う問題
Q4 「力のつり合い」と「作用・反作用」のちがいを、それぞれのはたらく物体の数に注目して説明しなさい。
模範解答
力のつり合いは、1つの物体に働く2つの力の関係。
作用・反作用は、2つの物体の間で働く力の関係。
出題意図
→ 「同じ大きさ・反対向き」とだけ書く生徒が多い。
→ “どこに働くか”を意識して書けるかが得点の分かれ目。
【出る⑤】応用・文章記述型(入試で頻出)
Q5 机の上に本が静止している。
① 本に働く力を2つ書きなさい。
② 「力のつり合い」と「作用・反作用」の両方を使って、
本と机の間の力の関係を説明しなさい。
模範解答
① 重力(下向き)と、机の垂直抗力(上向きの力)。
② 重力と机の垂直抗力は、どちらも本に働く2つの力でつり合っている。
本が机を押す力と、机が本を押し返す力は、2つの物体の間ではたらく力で、作用・反作用の関係にある。
出題意図
→ 一見同じ場面でも、“つり合い”と“作用・反作用”を区別して書けるかを確認。
→ 定期テスト・入試どちらでも定番の良問。
🌟やってみよう!確認テスト(チャレンジ問題)
① 次の現象を「慣性の法則」を使って説明せよ。
A. バスが急に発進したとき、体が後ろに倒れる。
B. 机の上のコインの下の紙をすばやく引くと、コインがその場に残る。
【解答】
①A:体が動かないままでいようとする慣性のため。
B:コインが止まったままでいようとする慣性のため。
② 次のうち、作用・反作用の関係にあるものをすべて選べ。
a. 地面を蹴ると自分の体が前に進む。
b. 手を広げて空気を押す。
c. 本が机に乗っている。
【解答】
② a 地面を蹴る力(足→地面)と地面が押し返す力(地面→足)なので、作用・反作用の関係
b 手が空気を押す力(手→空気)と空気が手を押しかえる力(空気→手)なので、作用・反作用の関係
c 本には下向きの重力と机の垂直抗力(上向きの力)がはたらいており、これらは同じ物体(本)にはたらく力なので、力のつり合い。

◆鶴ヶ谷教室 ☎252-0998
989-0824 宮城野区鶴ヶ谷4-3-1
◆幸 町 教室 ☎295-3303
983-0836 宮城野区幸町3-4-19
電話でのお問合せ AM10:30~PM22:30