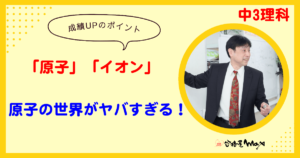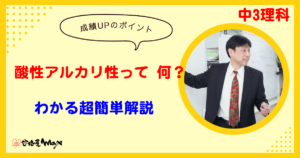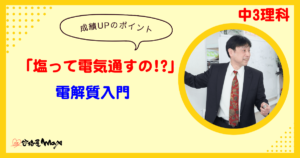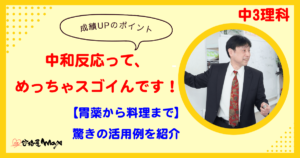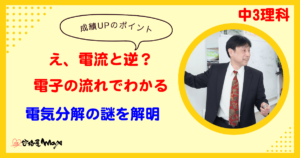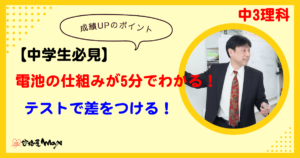「なんでスロープは楽なの?」――“仕事の原理”をやさしく完全理解!
👦ゆうと:「ねえ、あかり。駅のスロープって階段より楽に感じるけど、なんで?」
👧あかり:「良いところに気づいたね!それは仕事の原理で説明できるんだよ。」
① 仕事の原理ってなに?
👧あかり:「かんたんに言うとね、どんな道具を使っても、必要な仕事(エネルギー)の量は変わらないってことなんだ。」
👦ゆうと:「え、スロープでも他の方法や道具でも“楽になる”のに、同じなの?」
👧あかり:「うん。“楽”っていうのは必要な力が小さくなるってこと。でもその分、動かす距離が長くなるの。だから結局、力×距離=同じになるんだよ。」
📘 まとめ式
仕事(J)= 力(N) × 距離(m)
➡ 力が小さい ⇔ 距離が長い
➡ 全体の仕事量は同じ(=仕事の原理)
② スロープ(斜面)で考えよう
👧あかり:「40kg(=400N)の“お化けカボチャ”を3mの高さに上げるとしよう。斜面の長さは8mだよ。」
👦ゆうと:「重そうだね…!」
- 垂直に持ち上げる:400N × 3m = 1200J
- 斜面を使う:仕事=同じ1200J
→ 力=1200J ÷ 8m = 150N
👧あかり:「力は軽くなったけど、引く距離は長くなったよね。」
👦ゆうと:「“力×距離”が同じだから、結局エネルギーは変わらないのか!」
✅ 仕事の原理(斜面版)
垂直に持ち上げた仕事 = 斜面で持ち上げた仕事
③ 動滑車で考える
👧あかり:「次は動滑車だよ。これは“力が半分、距離が2倍”がキーワード!」
👦ゆうと:「なんで半分になるのかは、いまいちわからないなぁ。」
👧あかり:「それはこのあとでくわしく説明するね。🔎
→ 動滑車のしくみがわからない人は、下の“補足コラム”も読んでみよう!」
- 4kg(=40N)の物体を0.5m上げる
- そのまま上げる → 40N × 0.5m=20J
- 動滑車使用 → 力 20N、距離 1m
→ 20N × 1m=20J(同じ!)
👦ゆうと:「あ、やっぱり同じ!ラクになった分、たくさん引っ張ってるんだね。」
④ てこ(レバー)で考える
👦ゆうと:「てこって、理科でやった“支点・力点・作用点”のやつだよね?」
👧あかり:「そうそう! てこも“仕事の原理”で説明できるんだよ。」
① まずは身近なてこをイメージしてみよう
👧あかり:「シーソーや缶切り、ハサミも全部“てこ”の仲間なんだ。
てこは小さな力で大きなものを動かすための工夫なんだよ。」
👦ゆうと:「力が小さくなるなんてすごい!でもどうしてそうなるの?」
② 支点からの距離がカギ!
👧あかり:「支点(し点)から遠いほど、小さい力で動かせるんだ。
だから、長い棒を使うと“てこ”の力が大きくなるの。」
📘 てこのきほん式
力の大きさ × 力の腕の長さ = 重さ(作用点の力) × 重さの腕の長さ
これが“てこのつり合いの法則”だよ。
③ 数値で考えてみよう!
👧あかり:「じゃあ、例題で考えてみよう。」
問題:
支点から右に0.5mのところに20kg(=200N)のお米の袋を置きます。
左に2.0mの棒の先を押して持ち上げたいとき、どれくらいの力が必要でしょう?
🧮 考え方
お米の袋がされた仕事=200N×0.5m
人がした仕事=xN×2.0m
この2つは等しから、200N×0.5m=xN×2.0m
x=50N
👧あかり:「つまり、50Nの力で持ち上げられるの!
直接持ち上げると200Nも必要だったのに、4分の1の力でできたんだね。」
👦ゆうと:「すごい! でも何か代わりに損してる感じがするけど…?」
④ そう、“距離”が長くなる!
👧あかり:「そのとおり! 力が小さくなるかわりに、手を動かす距離が長くなるんだよ。」
同じ仕事量になるように、
- 米袋を0.2m(20cm)持ち上げると、
- 手の方は4倍の距離、つまり0.8m下げる必要がある。
仕事(力×距離)=200N×0.2m=40J
てこ側=50N×0.8m=40J
👧あかり:「ね? “力が4分の1になった分、距離が4倍”で、仕事の量は同じでしょ?」
👦ゆうと:「ほんとだ! “ラクになる=たくさん動かす”ってことなんだね!」
⑤ てこも「仕事の原理」にあてはまる!
📘 まとめ
| 比べ方 | 力 | 距離 | 仕事(力×距離) |
|---|---|---|---|
| 手で直接持ち上げる | 大きい(200N) | 短い(0.2m) | 同じ |
| てこを使う | 小さい(50N) | 長い(0.8m) | 同じ |
👧あかり:「てこもスロープや動滑車と同じ。“力を小さくすれば距離が長くなる”んだよ。」
👦ゆうと:「なるほど!力の比と距離の比が反対になるんだね。」
🪄図でイメージ(文字で表現)
↑ 200N(重さ)
■ 米袋
|
支点●──────────────◎ あかりが押す(50N)
0.5m 2.0m
👧あかり:「長い方(力の腕)が4倍だから、力は1/4でOK。でもその分、手を4倍動かすんだね。」
✅ まとめ(てこ版)
- 支点からの距離が長いほど、小さな力で動かせる。
- 力が小さくなるかわりに、動かす距離は長くなる。
- 結局、仕事(力×距離)の量は同じ=仕事の原理!
👦ゆうと:「“ラクになるけど、たくさん動かす”っていうのは、スロープや滑車と全く同じだね!」
👧あかり:「そう! てこも滑車も斜面も、“自然界のルール”は共通なんだよ。」
⑤ よく出る道具の関係まとめ
| 道具 | 力の大きさ | 距離 | 仕事の量 |
|---|---|---|---|
| 斜面(スロープ) | 小さくなる | 長くなる | 同じ |
| 動滑車 | 1/2になる | 2倍になる | 同じ |
| てこ(長い腕) | 小さくなる | 長くなる | 同じ |
📘 覚え方:
「力をへらすと、動かす距離がのびる。」
これが“仕事の原理”の正体!
🧭 よくあるミスTOP3
| ミス | 直し方 |
|---|---|
| ① kgのまま計算 | 100g=1Nに直す(例:40kg=400N) |
| ② cmのまま代入 | 必ずmに直す(例:20cm=0.2m) |
| ③ 動かす距離を取り違える | てこ・滑車・斜面の動かす側の距離 |
🔧 発展:合体問題に挑戦!(斜面+動滑車)
問題
長さ8m・高さ2mの斜面に、動滑車をつけて20kg(=200N)の荷物を持ち上げます。摩擦はなし。
① 垂直に持ち上げた仕事は?
② 引く力は?
③ 引く距離は?
解答
① 200N × 2m = 400J
② 斜面を使うと:400J ÷ 8m = 50N
→ 動滑車で力は1/2 → 25N
③ 斜面距離8m × 動滑車で2倍 → 16m
👦ゆうと:「おお!ラクになったけど、16mも引っ張るのか!」
👧あかり:「そう。道具を組み合わせても、“仕事の原理”は変わらないんだよ。」
🔍 目で見る“力と距離”のイメージ図
[垂直持ち上げ]
↑400N
■
|
3m
[斜面]
→(150N)________■
/
/
/
3m 高さ
[動滑車]
↓20N
○===■(荷物40N)
↑↑
2本で分担
💬 まとめ
- 「仕事の原理」=どんな道具を使っても仕事(力×距離)は同じ!
- 力を小さくした分だけ距離は長くなる。
- 1N=100g、距離はm単位に必ず直す!
- 入試の合体問題(斜面+滑車)でも考え方は同じ!
🪶補足コラム:動滑車(どうかっしゃ)のひみつ
🔎「動滑車ってどんなもの?」と思った人はここをチェック!
👦ゆうと:「“動滑車”って聞いたけど、よくわからない…。」
👧あかり:「じゃあ簡単に説明するね!」
① 動滑車とは?
「滑車」はロープをかけて重いものを動かす“車(くるま)”のこと。
中でも「動滑車(どうかっしゃ)」は、荷物といっしょに動く滑車のことだよ。
- 固滑車:天井に固定。力の向きだけ変える。
- 動滑車:荷物と一緒に動く。力が半分になるけど、距離が2倍になる。
② なぜ力が半分になるの?
荷物は2本のロープで支えられているから!
ロープが2本あれば、それぞれが半分ずつ力を分け合う。
例)荷物が400Nの重さなら、1本あたり200N。
→ 引く力は200NでOK!
③ なぜ距離が2倍になるの?
ロープを1m引くと、2本のロープの分だけ動く。
つまり荷物は 0.5mしか上がらない。
➡ 力が半分になるかわりに、距離が2倍!
➡ 「力×距離」は同じだから、仕事の量は変わらない。
④ まとめ
| 覚え方 | 内容 |
|---|---|
| 力の大きさ | 半分になる |
| 動かす距離 | 2倍になる |
| 仕事の量 | 同じまま |
| 理由 | 2本のロープで支えるから |
👧あかり:「“2本で支えるから半分の力でOK、でも2倍動かす!”って覚えよう!」
👦ゆうと:「うん、これなら忘れなさそう!」
💬 先生のまとめ
- 「仕事の原理」=どんな道具を使っても仕事(力×距離)は同じ!
- 力を小さくした分だけ距離は長くなる。
- 1N=100g、距離はm単位に必ず直す!
- 入試の合体問題(斜面+滑車)でも考え方は同じ!
👦ゆうと:「“仕事”って、結局“力と距離のバランス”なんだね!」
👧あかり:「そう!道具をうまく使えばラクになるけど、全体のエネルギー量は変わらない。それが自然の法則だよ。」
💬 Q&Aでわかる!「仕事の原理」の考え方
- Q1 力が小さくなるのに、なんで仕事の量は同じなの?
-
👦ゆうと:「スロープを使うと力が小さくなるのに、どうして仕事の量は同じなんだろう?」
👧あかり:「いい質問! “仕事”は“力×距離”で決まるでしょ? 力を半分にすると、距離を2倍にしないと同じ仕事量にならないの。」
👦ゆうと:「あっ、だから“力が小さいほど長く動かす”んだね!」
👧あかり:「そう。どんな道具を使っても“力×距離”が同じになる――これが仕事の原理の基本なの。」 - Q2 動滑車では、なんで力が半分になるの?
-
👦ゆうと:「動滑車って、どうして引く力が半分になるの?」
👧あかり:「ロープが2本で荷物を支えてるからだよ。2人で1つの荷物を持てば、1人あたりの力が半分になるでしょ? あれと同じ原理!」
👦ゆうと:「なるほど! 2本のロープが“力を分け合う”ってことなんだね!」
👧あかり:「そうそう。だから“2本なら1/2、3本なら1/3”って考えると、入試でもすぐ解けるよ。」 - Q3 てこで力が小さくなるのは、どうしてなの?
-
👦ゆうと:「てこって、支点から遠いほど軽く感じるよね? なんで?」
👧あかり:「支点から遠いほど“てこの腕の長さ”が長くなるから。長い棒は小さい力でも大きく動かせるでしょ? 力×距離のバランスで決まるの。」
👦ゆうと:「あっ、“力が小さいけど長く動かす”っていうスロープと同じ考え方だ!」
👧あかり:「その通り! “てこ”も“滑車”も“斜面”も、全部“仕事の原理”でつながってるんだよ。」 - Q4 どうして「距離」がそんなに大事なの?
-
👦ゆうと:「問題を解くときって、つい“力”ばかり見ちゃうけど、なんで“距離”がそんなに大事なの?」
👧あかり:「いいところに気づいたね。力が小さくても、距離を長くすれば同じエネルギーになる。つまり“距離”がエネルギーの使い方を決めるんだよ。」
👦ゆうと:「つまり、力だけじゃなくて“どれだけ動かしたか”もセットで考えるってこと?」
👧あかり:「そう! 物理は“力”と“距離”がペアで登場する。だから単位もN(ニュートン)とm(メートル)をセットで使うんだ。」 - Q5 道具を使ってもエネルギーが減らないの?
-
👦ゆうと:「道具を使うと楽になるんだから、エネルギーが減ってるように感じるけど?」
👧あかり:「実は“楽になる”=“エネルギーが減る”じゃないの。力は減っても、動かす距離がのびてるから、トータルの仕事量は変わらないの。」
👦ゆうと:「じゃあ、スロープでも滑車でも、使うエネルギーは同じなんだ!」
👧あかり:「そう。ただし、摩擦があるとちょっと多めに必要になるけど、それは“効率”の話。次の回でやろうね。」
🌟まとめ
- 「力が小さくなる=距離がのびる」
- 「道具が変わっても“仕事の量”は同じ」
- 「すべては“力×距離=一定”という考え方で説明できる」
- 「エネルギーは消えるわけじゃない、形を変えて使われるだけ」
✅先生からアドバイス
1️⃣ 仕事の公式は「仕事=力×距離」
→ 力の単位はN(ニュートン)、距離はm(メートル)。
→ 1N=100gとして計算する。
2️⃣ 「力を小さくすれば、距離が長くなる」
→ スロープ・動滑車・てこに共通する“仕事の原理”の考え方。
3️⃣ どんな道具を使っても、仕事の量(エネルギー)は同じ!
→ 使う力と距離が変わるだけ。
4️⃣ 動滑車では「力は1/2、距離は2倍」
→ ロープが2本で支えているから、1本あたりの力が半分になる。
5️⃣ てこでは「力の腕×力=重さの腕×重さ」
→ 腕の長さが4倍なら、力は1/4でOK。
→ ただし、動かす距離は4倍になる。
6️⃣ 単位変換ミスに注意!
→ cmをmに、kgをNに直してから計算。
→ 例:20kg=200N、20cm=0.2m
7️⃣ 摩擦があるときは、実際の仕事量は大きくなる!
→ 「仕事=力×距離」で求めた値よりも多くのエネルギーが必要。
🔹1. 計算基本パターン
- 「5Nの力で3m動かした」→ 仕事を求める(5×3=15J)
- 「400Nで3m上げた」→ 1200J
- 単位を変えて出す(cm・kgの混在に注意!)
🔹2. 仕事の原理の説明パターン
- 「スロープを使うと楽に感じるのはなぜ?」
→ 力が小さくなるかわりに、動かす距離が長くなるから。 - 「動滑車を使うと力が半分になる理由を説明せよ」
→ ロープが2本で荷物を支えるため、1本あたりの力が半分になる。 - 「てこを使うと小さい力で持ち上げられる理由」
→ 力の腕が長いから。
🔹3. 応用パターン(入試・後半範囲)
- 斜面+動滑車の組み合わせ(力を2段階で計算)
- てこの左右の距離比から力を求める問題
- 摩擦がある場合の比較問題(仕事量が大きくなる)
🔹4. よく出るひっかけ
- 力の向きと動く向きが違うと仕事は0!
(例:重い荷物を持って歩く → 仕事0) - 単位をそのまま代入して間違う(cm・kgに注意)
- “力が小さい=仕事が小さい”ではない!(距離が伸びる)
🧩得点アップのコツ
👧あかり:「計算が出ても、まず“力と距離”を見分けることが大事!」
👦ゆうと:「“仕事の原理=力×距離が同じ”を思い出せば、どんな道具の問題でも解けるね!」
👧あかり:「そう!入試では“なぜ力が小さくなるのか”を説明させる問題も多いから、“2本で支える”“腕が長い”の理由を言葉で書けるようにしよう!」
💡先生のひとこと
「仕事の原理」は“力と距離の関係”を問う基本単元。
計算式が出ても、考え方(力を減らす=距離をのばす)を理解していれば大丈夫だよ!
導入(短縮版🧮確認問題コーナー(中3理科:仕事の原理)
👧あかり:「ここまでの復習をしてみよう!」
👦ゆうと:「一問ずつ確かめながらやると、テスト前でも安心だね!」)
🔹① 用語の確認(基本のキホン)
Q1. 「仕事」とは、どんなときにしたことになる?
✅ 答え: 力を加えて、力の向きに物体を動かしたとき。
💬 解説: 力を出しても物が動かない(壁を押すなど)ときは、物理的な「仕事」にはならないよ。
Q2. 「仕事の原理」とはどんな法則?
✅ 答え: 道具を使っても、物体を動かすために必要な仕事の量(エネルギー)は変わらない法則。
💬 解説: 力を小さくした分、動かす距離が長くなる。だから「力×距離=一定」になる。
Q3. 動滑車を使うと、引く力と距離はどうなる?
✅ 答え: 力は半分、距離は2倍。
💬 解説: ロープが2本で荷物を支えるので力が半分になる。その代わり、2倍の距離を引く必要がある。
Q4. てこでは、どんなときに小さい力で動かせる?
✅ 答え: 力の腕(支点から力を加える場所までの距離)が長いとき。
💬 解説: 腕が長いほど、てこのはたらきが強くなる。力が小さくても同じ仕事ができる。
Q5. 仕事の単位は何?どんなとき1になる?
✅ 答え: 単位はジュール(J)。1Nの力で1m動かしたときに1J。
💬 解説: 仕事=力×距離 なので、N(ニュートン)×m(メートル)=J(ジュール)。
🔹② 計算問題(基本)
Q6. 5Nの力で3m物体を動かしました。仕事は何J?
✅ 答え: 15J
💬 解説: 仕事=力×距離=5×3=15J。単位もセットで覚えよう。
Q7. 40kgの荷物を3mの高さに持ち上げました。1N=100gのとき、仕事は?
✅ 答え: 1200J
💬 解説: 40kg=400N。よって、仕事=400×3=1200J。kg→N変換がポイント!
Q8. 20Nの力で物体を引き、仕事が160Jでした。
このとき、物体は何m動かしましたか?
✅ 答え: 8m
💬 解説:
仕事=力×距離
→ 距離=仕事÷力=160÷20=8m
Q9. 400Nの物体を3m持ち上げると1200J。スロープの長さが8mのとき、必要な力は?
✅ 答え: 150N
💬 解説: 仕事=力×距離 ⇒ 1200=力×8 ⇒ 力=150N。力が小さくなる分、距離が長くなる。
Q10. 動滑車を使って40Nの物体を0.5m持ち上げます。引く力と距離は?
✅ 答え: 力=20N、距離=1m
💬 解説: 力は半分、距離は2倍。動滑車の基本関係式!
🔹③ 応用(考え方)
Q11. てこで20kg(=200N)の米袋を持ち上げます。
支点から米袋までが0.5m、力を加える場所が2mのとき、必要な力は?
✅ 答え: 50N
💬 解説: 200×0.5=x×2.0 → x=50N。
力の腕が4倍だから、力は1/4でOK。
Q12. 「力を半分にすると距離が2倍になる」のはなぜ?
✅ 答え: 仕事(力×距離)の量を同じに保つため。
💬 解説: 力が小さくなれば、その分たくさん動かさないと同じエネルギーにならない。これが「仕事の原理」。
Q13. 「重い荷物を持って歩く」場合、仕事をしている?
✅ 答え: していない。
💬 解説: 力の向き(上)と動く向き(横)がちがうから、物理的には仕事にならない。
Q14. 摩擦があるとき、仕事の量はどうなる?
✅ 答え: 大きくなる。
💬 解説: 摩擦をこえる分の力も必要になるため、エネルギーが多く必要になる。
Q15. 「仕事の原理」は、どんな道具にも共通している?
✅ 答え: 共通している。
💬 解説: 斜面・滑車・てこ、すべて「力を減らすかわりに距離をのばす」。この関係が共通ルール。
👧あかり:「これができたら、“仕事の原理”はもうバッチリ!」
👦ゆうと:「うん!あとはミスしやすい単位変換だけ気をつけよう!」
🚀チャレンジ問題(入試レベル)
👦ゆうと:「“仕事の原理”の計算 もうすこしやってみない。」
👧あかり:「じゃあ、本番レベルのチャレンジ問題で練習してみよう!」
🔹Q1. 重さ200Nの荷物を、長さ5m・高さ1mのスロープで持ち上げます。
このとき、スロープ斜面に平行に引く力はいくらですか?
(摩擦はないものとします)
✅ 答え: 40N
💬 解説:
仕事=力×距離=200×1=力×5
→ 力=200×1÷5=40N
👉 高さが1/5だから、必要な力も1/5。
斜面を長くすると、力が小さくなるけど距離はのびる。
🔹Q2.重さ60Nの物体を、動滑車を2つ使って持ち上げました。
動滑車が2つなので、ロープは4本で支えられています。
このとき、引く力はいくらになりますか?(摩擦はなし)
✅ 答え: 15N
💬 解説:
ロープが4本なら、荷重を4等分する。
→ 60N ÷ 4 = 15N
👉 ただし距離は4倍になる。
“力が小さくなる=距離がのびる”が仕事の原理の基本。
🔹Q3:スロープ+動滑車の組み合わせ
重さ120Nの荷物を、長さ6m・高さ2mのスロープの上に動滑車をつけて引き上げます。
動滑車は2本のロープで支えられています(摩擦はないものとします)。
このとき、荷物を引く力はいくらですか?
✅ 答え: 20N
💬 解説:
1️⃣ スロープだけの場合:
力 = 120 × 2 ÷ 6 = 40N
2️⃣ 動滑車をつけると力が半分になる。
40 ÷ 2 = 20N
👉 結論: 20N
スロープで力を1/3に、動滑車でさらに1/2にできる。
でも距離は6m×2=12mになる!
🔹Q4:てこ+動滑車の組み合わせ
てこで重さ80Nの荷物を持ち上げます。
支点から荷物までの距離が0.4m、力を加える点までが1.6mです。
さらに、その力の部分に動滑車(2本で支える)を取り付けて引き上げます。
荷物を持ち上げるのに必要な力はいくらですか?
✅ 答え: 10N
💬 解説:
1️⃣ てこだけの場合:
80×0.4=x×1.6 → x=20N
2️⃣ 動滑車で半分になる:
20 ÷ 2 = 10N
👉 結論: てこの腕で1/4、滑車でさらに1/2、
合わせて 1/8の力 で持ち上げられる!
💡アドバイス
・必ず「単位」をそろえて計算する(Nとm)
・考え方は「力が小さくなった分、距離が長くなる」
・問題を見たら、まず どの道具(斜面・滑車・てこ) の話かを整理して考えること!
🎬エンディングストーリー
👦ゆうと:「ふぅ〜、今日の“仕事の原理”は頭使ったな〜。
でもさ、これで僕も“仕事名人”になれた気がする!」
👧あかり:「え、ゆうとが“仕事名人”? それ、部屋の掃除もしない人が言う?😅」
👦ゆうと:「いやいや、今日はノート3ページも書いたんだよ!
“仕事=力×距離”だから、シャーペンを動かした距離もちゃんとカウントしていいでしょ!」
👧あかり:「…それ、物理的には“仕事”になるけど、テストの点にはならないからね(笑)」
👦ゆうと:「うわ〜、やっぱりそこ突っ込むか〜!
でも、今日の俺はちょっと違うぞ。力が小さくても、コツコツ距離をのばせば“仕事の量”は増えるんだ!
だから僕も、“少しずつ続ける”作戦で頑張る!」
👧あかり:「お、いいこと言うじゃん!
勉強も同じだよ。短時間でもコツコツ積み重ねれば、必ず力になる。
“力を半分にしても、距離を2倍”――努力も同じで、小さな努力を長く続けることが大きな成果につながるんだよ。」
✨今日も小さな一歩を積み重ねていきましょう。
勉強も「力×距離」です。
いきなり大きな力を出すよりも、毎日コツコツ続ける距離をのばすほうが、結果は大きくなります。
少しずつの努力が積み重なって、やがて「できた!」という大きな力に変わります。