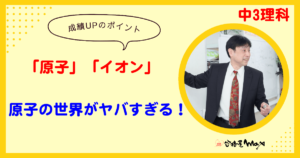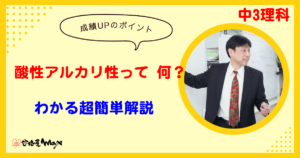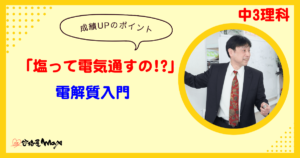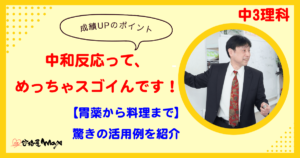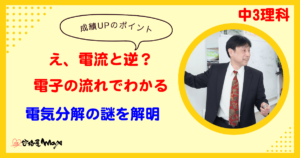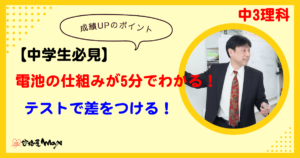🧩第2弾:「仕事の原理」を使ってみよう!
~スロープ・動滑車・てこを使いこなす!~
👦ゆうと:「あかり、この前“仕事の原理”の話を聞いて、なるほど~と思ったけど…どうやって実際に使うの?」
👧あかり:「いい質問!今日は“力と距離の関係”を、スロープ・動滑車・てこの3つで実際に計算してみよう!」
① スロープで考える「仕事の原理」
👧あかり:「スロープは“力を小さくする代わりに距離をのばす”代表的な道具だね。
たとえば3mの高さに荷物を上げたいとき、8mの斜面を使えば軽い力で運べるよ。」
📘 ポイント
- 仕事=力×距離
- どんな方法でも、仕事の量(エネルギー)は同じ
🧮実践問題①:スロープを使って持ち上げよう
問題
40kg(=400N)のお化けカボチャを3mの高さまで持ち上げます。
斜面の長さは8m。摩擦はなし。
① 仕事の量は?
② 引く力は?
解答・解説
① 仕事=400N×3m=1200J
② 1200J=x×8m
→ x=150N
👧あかり:「力は400N→150Nに小さくなったけど、距離は8mにのびたね!」
👦ゆうと:「“楽だけど長い”ってこういうことなんだ!」
🔹問題①(基礎)
重さ20kg(=200N)の荷物を、高さ1.5mの台の上に載せます。
斜面の長さが3mのとき、必要な力を求めましょう。
答え:100N
解説:
仕事=力×距離=200×1.5
→ 力=300÷3=100N
👉 力が半分、距離は2倍。スロープの基本パターン!
🔹問題②(標準)
重さ40kg(=400N)の荷物を高さ2mの棚に上げます。
斜面の長さが5mのとき、必要な力は?
答え:160N
解説:
仕事=400×2=800J
→ 力=800÷5=160N
👉 斜面を長くすればするほど、力は小さくなる!
🔹問題③(応用)
重さ60kg(=600N)の荷物を、長さ10m・高さ2.5mの斜面で引き上げるとき、必要な力を求めましょう。
答え:150N
解説:
仕事=600×2.5=1500J
→ 力=1500÷10=150N
👉 仕事の原理「力×距離=一定」で、いつも計算できる!
② 動滑車を使う「仕事の原理」
👧あかり:「動滑車は、荷物といっしょに動く滑車だよ。
2本のロープで荷物を支えるから、引く力は半分になるんだ。」
📘 ポイント
- 力が1/2になる
- 代わりに距離は2倍になる
- 仕事の量は変わらない
🧮実践問題②:動滑車を使って持ち上げよう
問題
4kg(=40N)の物体を0.5m持ち上げます。
動滑車を使うとき、必要な力と引く距離を求めよう。
解答・解説
① そのまま持ち上げた場合:40N×0.5m=20J
② 動滑車を使うと:力=20N、距離=1m
→ 20N×1m=20J
👦ゆうと:「力が半分でも、仕事の量は同じなんだ!」
👧あかり:「そう!“2倍動かす”ことでバランスがとれてるの。」
⚙️【動滑車編】~ロープの本数で力が変わる!~
🔹問題①(基礎)
重さ4kg(=40N)の荷物を動滑車で持ち上げます。
必要な力と、1m持ち上げるためにロープをどれだけ引くかを求めましょう。
答え:力=20N、距離=2m
解説:
ロープ2本で支えるから、力は1/2、距離は2倍。
→ 仕事=20×2=40J(変わらない)
🔹問題②(標準)
重さ30kg(=300N)の荷物を動滑車で2m持ち上げます。
① 引く力 ② ロープを引く距離 を求めましょう。
答え:①150N ②4m
解説:
力は半分、距離は2倍。
→ 仕事=300×2=600J
→ 150×4=600J(OK!)
🔹問題③(応用)
重さ90Nの荷物を、動滑車を2つ使って(ロープ4本で支える)持ち上げます。
荷物を1m持ち上げるための力と距離を求めましょう。
答え:力=22.5N、距離=4m
解説:
4本で支える→力は1/4、距離は4倍。
→ 90÷4=22.5N
→ 仕事=22.5×4=90J(同じ!)
③ てこを使う「仕事の原理」
👧あかり:「てこは“支点”からの距離を使って力を変える道具。
支点から遠いほど、小さい力で動かせるんだよ。」
📘 ポイント
- 力×力の腕=重さ×重さの腕
- 力の腕を長くすれば、力を小さくできる
- でも、その分、動かす距離は長くなる
🧮実践問題③:てこで米袋を持ち上げよう
問題
20kg(=200N)の米袋を、てこで20cm(=0.2m)持ち上げます。
力の腕は2m、重さの腕は0.5mのとき、必要な力と動かす距離を求めましょう。
解答・解説
① 力×2.0=200×0.5
→ 力=50N
② 腕の長さの比=1:4 ⇒ 距離も4倍
→ 0.2m×4=0.8m
👧あかり:「力は1/4でOK!でも距離は4倍動かすんだね。」
👦ゆうと:「ほんとだ。“力をへらすと距離がのびる”って、てこも同じなんだ!」
⚖️【てこ編】~支点からの距離で勝負!~
🔹問題①(基礎)
20kg(=200N)の荷物をてこで持ち上げます。
重さの腕が0.5m、力の腕が2mのとき、必要な力を求めましょう。
答え:50N
解説:
200×0.5=x×2.0
→ x=50N
👉 腕が4倍長いから、力は1/4!
🔹問題②(標準)
重さ60kg(=600N)の荷物を、支点から0.3mの位置に置きます。
力の腕を1.5mにしたとき、必要な力と手を動かす距離を求めましょう。
荷物の上がる高さは10cm(=0.1m)です。
答え:力=120N、距離=0.5m
解説:
600×0.3=x×1.5 → x=120N
距離比1:5 → 手の方が0.1×5=0.5m動く!
🔹問題③(応用)
重さ100kg(=1000N)の岩を、支点から0.4mの位置に置き、
力の腕を2.0mにして持ち上げます。岩を0.2m上げたいとき、
必要な力と手の動く距離を求めましょう。
答え:力=200N、距離=1.0m
解説:
1000×0.4=x×2.0 → x=200N
距離比1:5 → 手の方が0.2×5=1.0m動く!
👉 どんなに重くても、てこの原理で力は5分の1にできる!
④ まとめ:「どんな道具でも仕事は同じ」
| 道具 | 力 | 距離 | 仕事の量 |
|---|---|---|---|
| スロープ(斜面) | 小さくなる | 長くなる | 同じ |
| 動滑車 | 1/2になる | 2倍になる | 同じ |
| てこ | 小さくなる | 長くなる | 同じ |
👧あかり:「道具が変わっても“力×距離=一定”。これが仕事の原理だよ。」
👦ゆうと:「つまり、楽になるってことは、それだけ長く動かしてるってことか!」
🔥チャレンジ問題(入試レベル)
👧あかり:「さあ、いよいよ入試レベル!スロープ・滑車・てこが“組み合わさった”問題で、仕事の原理をしっかり使えるか試してみよう!」
⚙️チャレンジ① スロープ+動滑車の組み合わせ
重さ60kg(=600N)の荷物を、長さ6m・高さ2mのスロープの上に引き上げる。
ただし、動滑車を1つ使って引く。摩擦は考えない。
このとき必要な力を求めよう。
答え:100N
解説:
スロープの傾きで力は 600×(2÷6)=200N
さらに動滑車で半分 → 200÷2=100N
👉「スロープ+動滑車」は“2段階の減らし方”でOK!
⚙️チャレンジ② てこ+動滑車の組み合わせ
重さ100kg(=1000N)の岩をてこで持ち上げる。
岩の腕0.5m、力の腕2m。さらに、力を加えるところに動滑車をつけて引く。
必要な力を求めよう。
答え:125N
解説:
てこだけなら → 1000×0.5=x×2 → x=250N
動滑車で半分 → 250÷2=125N
👉 てこ+動滑車の“二段活用”で、力は1/8になる!
⚙️チャレンジ③ スロープ+てこの組み合わせ
重さ120kg(=1200N)の荷物を、長さ8m・高さ2mのスロープの上に乗せた後、
支点0.3m、力の腕0.9mのてこで持ち上げる。
スロープを引く力と、てこを押す力を求めよう。
答え:
①スロープを引く力=300N
②てこを押す力=100N
解説:
① スロープ:800×(2÷8)=300N
② てこ:300×0.3=x×0.9 → x=100N
👉 道具が違っても「力×距離=一定」で必ず計算できる!
🧠用語の確認(まとめ&覚える語句)
👧あかり:「最後は“用語”を確認しよう!理科のテストでは、公式だけでなく“用語”も出るからね。」
🔸基本用語チェック
仕事
力を加えて物体を動かしたときにしたこと。力×距離で求める。単位:J(ジュール)
仕事の原理
どんな道具を使っても、仕事の量(力×距離)は同じになるという法則。
てこの原理
力×力の腕=重さ×重さの腕。腕が長いほど小さい力で動かせる。
動滑車の原理
ロープの本数が多いほど力は小さくなるが、引く距離はその分長くなる。
斜面の原理
斜面を長くするほど、必要な力は小さくなる。
支点
てこの回転の中心となる点。
動滑車
| 荷物と一緒に動く滑車。引く力は半分、距離は2倍になる。 |
定滑車
固定されていて、力の向きを変えるだけの滑車。力の大きさは変わらない。
🔸重要ポイントまとめ
- 「力×距離=一定」
- 「力を小さくした分、距離がのびる」
- 「道具を変えても、仕事の量は変わらない」
- 「効率」は摩擦などで変わる(次回テーマ!)
👦ゆうと:「なるほど~。全部“力と距離”でつながってるんだ!」
👧あかり:「そう。だから公式を覚えるより、“考え方”をマスターすれば何でも解けるよ!」
💬 まとめ
“楽に動かす”とは、“距離をのばして力をへらす”ということ。
どんな道具でも、自然のルール「力×距離=一定」を忘れなければ大丈夫!
💡ここだけは絶対押さえろ!
仕事:力 × 距離(単位:J)
仕事の原理:力×距離=一定
てこの原理:力×力の腕=重さ×重さの腕
動滑車の原理:ロープの本数が多いほど力は小さくなる(2本なら1/2、3本なら1/3)
斜面の原理:高さが同じなら、斜面が長いほど力は小さくなる
👉 道具が違っても、すべて「力×距離=一定」でつながっている!
🧾テストではこう出る!
① 計算問題:「力×距離」の関係を使って求める
② 比の問題:「腕の長さの比」「ロープ本数の比」を使って求める
③ 記述問題:「どんな道具を使っても仕事の量は同じ」と説明させる
④ 図の問題:斜面・滑車・てこのどこに力がかかっているかを読み取る
⑤ 単位・用語問題:「仕事」「仕事の原理」「支点」「動滑車」「定滑車」などを確認
👧あかり:「この5パターンが定期テストにも入試にも必ず出るよ!」
👦ゆうと:「“力×距離=一定”を覚えておけば、どんな問題もへっちゃらだね!」
🍀ひとこと
「仕事の原理」は、“力を小さくする代わりに距離をのばす”という、自然の中のバランスの法則です。
勉強も同じ。すぐに結果を出そうとして近道を探すより、コツコツと続けた努力のほうが確実に力になります。
焦らず、一歩ずつで大丈夫。
その一歩一歩が、君の“学力というエネルギー”になっていくよ。
👩🏫 「がんばることは、ムダにならない」――先生はそれを何度も見てきました。
今日の勉強も、その一歩。よくここまで読んだね、えらいぞ!