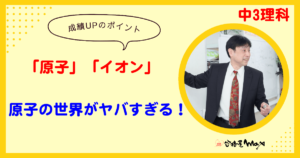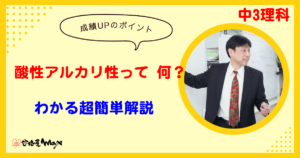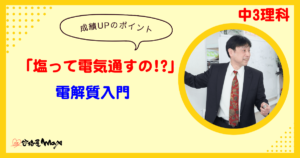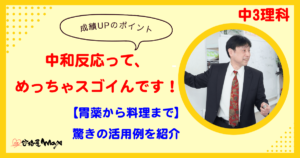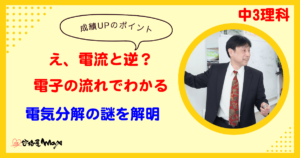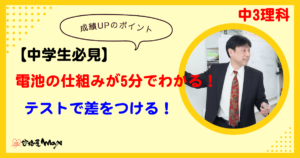プールで耳が痛くなったり、お風呂で体が軽く感じたりしたことはありませんか? 実はそれ、“水の力”が関係しているんです。 今回は中3理科の重要単元「水圧」と「浮力」を、ストーリーでやさしく解説します! アルキメデスの原理までスッキリわかるので、定期テストや高校入試対策にもピッタリです。
👦 ゆうと:「ねぇあかり、プールで潜ると耳がキーンってするの、なんでだろう?」
👧 あかり:「それはね、“水圧”っていう力のせいなんだよ。
今日は“水圧”と“浮力”の2つの力をいっしょに見ていこう!」
① 水圧ってなに?深くなるほど強くなる力!
👦 ゆうと:「水圧って…水が押す力ってこと?」
👧 あかり:「その通り! 水って重いから、深いところほど上からどんどん重さがかかってくるんだ。
だから、水の中では下に行くほど“押す力=水圧”が強くなるんだよ。」
🧪 ペットボトルで実験してみよう!
1本のペットボトルの側面に、上・中・下に3つの穴をあけて水を入れてみよう。
すると——
水圧.jpg)
👦 ゆうと:「あっ、下の穴から出る水の勢いが一番強い!」
👧 あかり:「でしょ? 下の方は水圧が大きいから、水が勢いよく出るんだよ。」
💡 ポイント
- 水圧は水の重さが原因で生まれる。
- 水深が深くなるほど、水圧は強くなる。
- 水圧は上下左右、あらゆる方向からはたらく!
② 浮力ってなに?浮かせる力のひみつ!
👦 ゆうと:「お風呂に入ると、体が軽くなる気がするけど、あれも水圧?」
👧 あかり:「いいところに気づいたね! それは“浮力”っていう力だよ。
水の中のものは、いつも下から押し上げられているんだ。」
🧪 ためしてみよう!
空のペットボトルにふたをして、水に沈めてみよう。
👦 ゆうと:「押さえつけると、グッと押し返される感じがする!」
👧 あかり:「それが“浮力”! 下から押し上げる力があるんだよ。」
💡 ここで注意!
浮力の大きさは水深とは関係ないんだ。
深く沈めても、浮力そのものは変わらない。
でも、深くなるとまわりからの水圧が大きくなるから、ペットボトルのへこみが大きくなる。
③ 浮力の正体をさぐれ!アルキメデスの原理
👦 ゆうと:「なんで浮力が生まれるの?」
👧 あかり:「それはね、水圧の“上と下の差”があるからなんだ。」
下の方は、上に水が多いから水圧が強く、上の方は、それより上の水が少ないから水圧は弱い。
その差が“下からの押し上げ”になる。これが浮力の正体!
👧 あかり:「そしてね、浮力の大きさは“押しのけた水の重さ”と同じなんだ。
この決まりを“アルキメデスの原理”っていうの。」
👦 ゆうと:「へぇ~! 水10㎤を押しのけたら、その重さ分の10gの浮力がはたらくんだ!」
👧 あかり:「その通り! 船が浮くのも、この原理を使ってるんだよ。」
④ まとめ
🪣 水圧 … 深くなるほど強くなる!
🛶 浮力 … 水圧の差によって生まれる、浮かせる力!
⚖️ アルキメデスの原理 … 浮力の大きさは押しのけた水の重さに等しい!
👧 あかり:「潜水艦が沈んだり浮かんだりできるのも、この2つの力を調整してるからなんだよ。」
👦 ゆうと:「なるほど、水の中って力がいっぱい働いてるんだね!」
👧 あかり:「そう! 次にお風呂に入るときは、水の押す力や浮かせる力を感じてみよう!」
💡水圧と浮力の本質にせまるQ&A
- Q1. 👦「どうして深いところほど水圧が強くなるの?」
-
👧 あかり:「いい質問だね! 水圧って、“上にある水の重さ”が関係してるんだよ。」
👦 ゆうと:「上にある水の重さ…?」
👧 あかり:「そう。たとえば水の中で1m深く潜ると、その上には1mぶんの“水の重さ”がのってくる。
だから深くなればなるほど、上から押される力=水圧が大きくなるんだ。」👦 ゆうと:「なるほど。空気よりも水の方が重いから、ちょっと潜っただけでも耳が痛くなるんだね!」
👧 あかり:「そういうこと! 水の重さが押してくる力、それが“水圧”なんだよ。」
- Q2. 👦「水圧って、下からも横からもかかるの?」
-
👧 あかり:「うん、水圧はあらゆる方向からはたらくよ。」
👦 ゆうと:「上から押されるイメージしかなかった!」
👧 あかり:「実は、水の中の物体は“全方向から”押されてるの。
だから、ペットボトルを深く沈めると、へこむときは“上下左右ぜんぶ”から押されてるんだ。」👦 ゆうと:「なるほど〜。水の中って、まるで空気の中みたいに包まれてる感じなんだね。」
👧 あかり:「その感覚、すごく正しい! 水中では、全身で水圧を感じてるんだよ。」
- Q3. 👦「浮力って、どうして下から押し上げる力になるの?」
-
👧 あかり:「それはね、水の“下の方が水圧が強い”からなんだ。」
👦 ゆうと:「つまり、下から押す力の方が、上から押す力よりも強いってこと?」
👧 あかり:「そう! 水の中の物体には、上面にも下面にも水圧がかかるけど、
下の方が深いぶん、水圧が大きい。
その“差”が、上向きの力=浮力になるんだ。」👦 ゆうと:「へぇ〜、浮力って水圧の“バランスのズレ”なんだね!」
👧 あかり:「その通り! だから“浮力は水圧の差で生まれる力”なんだよ。」
- Q4. 👦「浮力って、水の深さによって変わるの?」
-
👧 あかり:「いいところに気づいたね! 実はね、深さを変えても浮力の大きさは変わらないんだ。」
👦 ゆうと:「えっ!? 水圧は深いほど強いのに、浮力は変わらないの?」
👧 あかり:「うん。浮力の大きさは“押しのけた水の重さ”できまるから、
同じ体積のものを沈めれば、どの深さでも同じ浮力がはたらくんだよ。」👦 ゆうと:「なるほど、深くしても“押しのけた水の量”は同じなんだね。」
👧 あかり:「そう。だから潜水艦は、体積を変えずに“中の空気量”を調整して沈んだり浮いたりしてるんだ。」
- Q5. 👦「浮くものと沈むものの違いって、結局なに?」
-
👧 あかり:「ポイントは“重力と浮力のどちらが強いか”だよ。」
👦 ゆうと:「たとえば軽いスイカは浮くけど、石は沈むよね?」
👧 あかり:「うん。物体にかかる浮力は“押しのけた水の重さ”と同じ。
だから、その物体の重さよりも押しのけた水の重さが大きければ——浮く!
逆に、物体の方が重ければ——沈む! ってわけ。」👦 ゆうと:「あぁ〜、浮くか沈むかは“どっちの力が勝つか”で決まるんだ!」
👧 あかり:「正解! つまり、浮力と重力の“力くらべ”が結果を決めてるんだよ。」
🧠先生のここだけは押さえろ!
① 水圧は深さによって変わる!
👉 深いほど水圧は大きくなる。
これは「上にある水の重さ」が増えるから。
ペットボトルの穴実験で、下の穴ほど水が勢いよく出るのはこのため!
② 水圧は全方向にかかる!
👉 下からだけでなく、左右・上からも同じように水圧がかかる。
だから潜水艦やダムの壁は、あらゆる方向の力に耐えるように作られている。
③ 浮力は“水圧の差”で生まれる!
👉 水中の物体には、上からの水圧より下からの水圧の方が強い。
その差が、上向きの力=浮力になる!
④ 浮力の大きさは「押しのけた水の重さ」と等しい!
👉 これが「アルキメデスの原理」。
つまり、水に沈んだ“体積”で浮力が決まる。
⑤ 浮く・沈む・浮かばないの違いは力のバランス!
👉
・浮力 > 重力 → 浮く
・浮力 = 重力 → 水中で止まる
・浮力 < 重力 → 沈む
このバランスが理解できれば、潜水艦や船の仕組みもスッキリ!
📘テストにここが出るぞ!
① 水圧の関係を問う作図問題!
🔸 ペットボトル実験の図から「どの穴の勢いが強いか」を選ぶ問題。
→ 正解は「一番下の穴(深いほど水圧が大きい)」。
② 水圧の向きに関する記述問題!
🔸 「水圧はどの方向に働いているか」
→ 答え:「あらゆる方向に働く(上下左右すべて)」。
③ 浮力の原因を問う説明問題!
🔸 「なぜ浮力がはたらくのか」
→ 答え:「上面と下面の水圧の差によって、上向きの力が生じるから」。
④ アルキメデスの原理の計算問題!
🔸 例:「体積200㎤の物体にはたらく浮力は何gか(密度1.0g/㎤)」
→ 答え:200g(押しのけた水の重さと同じ)。
⑤ 浮力と重力の関係を問う選択問題!
🔸 「物体が水中で静止しているとき、浮力と重力の関係は?」
→ 答え:「大きさが等しい」。 静止している→ 釣り合っている
🗝️ 先生のひとこと
「水圧」は“深さと方向”、「浮力」は“水圧の差と体積”で決まる!
ここを混同しないことが、テスト高得点のカギ!
🧩確認問題(基本・一問一答+解説付き)
① 水の中で、深くなるほど大きくなる力を何という?
👉 答え:水圧(すいあつ)
💬 解説:
水の上にはたくさんの水の重さがあるため、深くなるほど押す力(水圧)が強くなる
② 水圧が生じるのは、水の( )が原因である。
👉 答え:重さ
💬 解説:
水は重いので、その重さが下の方にかかることで水圧が生まれる。
③ ペットボトルの側面に穴を開けたとき、水の勢いが一番強くなるのはどの位置?
👉 答え:一番下の穴
💬 解説:
深いほど上にある水の重さが増えるので、水圧が大きくなり、水の勢いも強くなる。
④ 水圧はどの方向に働く?
👉 答え:あらゆる方向(上下左右すべて)
💬 解説:
水はどの方向にも流れようとする性質があるため、水圧も全方向に働く。
⑤ 水中の物体に上向きに働く力を何という?
👉 答え:浮力(ふりょく)
💬 解説:
浮力は、水中の物体を上へ押し上げようとする力のこと。
⑥ 浮力は、物体の上面と下面に働く( )の差によって生じる。
👉 答え:水圧
💬 解説:
下面の方が水圧が大きいため、上向きの力(浮力)が生まれる。
⑦ 浮力の大きさは、物体が押しのけた( )の重さに等しい。
👉 答え:水(液体)
💬 解説:
押しのけた水の体積が大きいほど、浮力も大きくなる。これを「アルキメデスの原理」という。
⑧ ⑦の問題で説明した原理を何という?
👉 答え:アルキメデスの原理
💬 解説:
浮力の大きさは、押しのけた水の重さに等しいという原理。船や潜水艦の仕組みの基本にもなっている。
⑨ 物体が水中で静止しているとき、浮力と重力の関係は?
👉 答え:大きさが等しい(浮力=重力)
💬 解説:
上向きの浮力と下向きの重力がつり合っているため、水中で止まっている。
⑩ 浮く・沈むの違いはどんな力のバランスで決まる?
👉 答え:浮力と重力のバランス
💬 解説:
- 浮力 > 重力 → 浮く
- 浮力 = 重力 → 水中で止まる
- 浮力 < 重力 → 沈む
🚀チャレンジ問題(応用レベル)
🧮【第1問:計算問題】
問題: 体積が200㎤の立方体を水に完全に沈めたとき、
この物体にはたらく浮力の大きさは何gか?
(※水の密度=1.0g/㎤ とする)
答え: 200g
解説:
浮力の大きさは、押しのけた水の重さと等しい。
この立方体が沈めた体積は200㎤なので、
押しのけた水の重さも200g。
したがって、浮力=200g。
👉 公式: 浮力(g)=押しのけた水の体積(㎤)×1.0
🧪【第2問:実験問題】
問題:ペットボトルに3つの穴を開け、水を入れて観察した。
すると、下の穴ほど水が強く飛び出した。
この現象から、何がわかるといえるか?
答え:
水圧は深いほど大きいということがわかる。
解説:
水は重いため、下の方ほど上にある水の重さが増える。
そのため、下の穴ほど水圧が大きくなり、水が勢いよく出る。
👉 ポイント:
「水圧 と 深さは比例する」=深くなると水圧が強くなる
✍️【第3問:文章説明問題】
問題:船が鉄でできているのに、水に浮くのはなぜですか?
答え:
船全体の形が大きく、押しのける水の量(体積)が多いため、
浮力が重力より大きくなるから。
解説:
鉄は重いが、船の内部は空気が多く、平均の密度は小さい。
そのため、船が押しのける水の重さ(浮力)が船全体の重さ(重力)より大きくなり、浮く。
👉 キーワード:
「密度」「押しのけた水の量」「浮力と重力のバランス」
🎬エンディングコーナー:ゆうと&あかりのひとやすみ
👦 ゆうと:「あ〜、今日もお風呂で“科学の探究”してくるか〜!」
👧 あかり:「また何かやらかす予感しかしないんだけど…。」
👦 ゆうと:「まずは浮力の実験!シャンプーボトル、浮くかな〜!」
(ちゃぽん…)
👦 ゆうと:「おおっ!浮いた!俺と同じで、やっぱり軽いんだな!」
👧 あかり:「……ボトルは“空気が入ってる”からでしょ。」
👦 ゆうと:「じゃあ次は水圧!ペットボトルに穴あけて〜……(ぷしゅーっ!)」
👧 あかり:「うわっ、やめて!お風呂が大洪水になるー!」
👦 ゆうと:「大丈夫、科学のためだから!」
👧 あかり:「……そのセリフ、先生に言って怒られてきて。」
👦 ゆうと:「あっ、そうだ!アルキメデスがこの原理”を思いついたとき、
お風呂に入っていて『ユリーカ!(わかった!)』って叫んだんだよね!」
👧 あかり:「そうそう。それで町中を走り回ったらしいよ。」
👦 ゆうと:「へぇ〜。じゃあ俺も今夜、お風呂で“ゆーとーか!”って叫んで走り回るか!」
👧 あかり:「……お願いだから服は着てからにしてね。」
🫧 先生のひとこと
勉強って、“わかる”って思えた瞬間が一番楽しい時間です。
みんなも自分だけの「ユリーカ!」を見つけていこう!