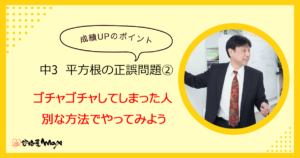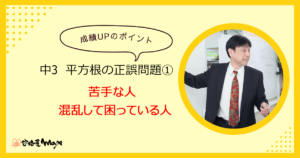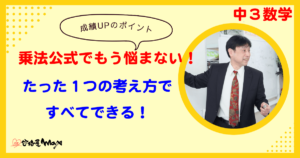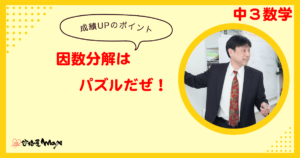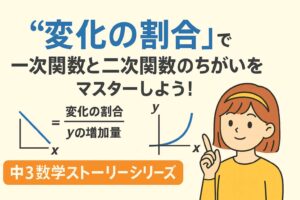中3数学 二次関数の変域を完全攻略|0チェックで最大・最小を一発判断
本ページでは、二次関数 y = ax² の変域を 0を含むかどうかのチェックとaの符号、そして「0と0から遠い方のx」 の3ステップで素早く見抜く方法を解説します。放物線の形・頂点(x=0)の性質・対応表の書き方まで、 ストーリー対話でわかりやすく整理。グラフを描かなくても、最大値・最小値をミスなく判断できます。
このページで身につくこと
- 0チェックで「頂点が範囲内か」を即判断
- a > 0 / a < 0 で最小・最大の向きを判断
- 「0と遠い方のx」の2点だけで変域を決めるコツ
- 対応表で計算ミスを防ぎ、検算まで完結
関連キーワード
中3数学, 二次関数, 変域, 最大値, 最小値, 放物線, 頂点, aの符号, 0チェック, 対応表, 定期テスト対策, 高校入試, 応用問題, グラフを描かない解法
💬 ゆうと&あかりのストーリー解説
二次関数の変域・応用編
テーマ:0チェックと「遠い方のx」で最大・最小を見抜く!
👦 ゆうと:「うわ、また“変域”の問題か…。
今回は、関数 y=ax² で、x の範囲が −2 ≦ x≦≤ 3 のとき、y の範囲が b≦ y≦ 3 になるっていう問題だね。
a と b を求めるって書いてあるけど、どうすればいいんだろう?」
👧 あかり:「いい質問だね!
このタイプの問題は、“範囲に0があるかないか”と “グラフの形をイメージすること” が大事だよ。
まず、“範囲に0があって、最大値が3”って書いてあるところから考えてみよう。」
👦 ゆうと:「最大値が3ってことは……下に開く放物線(a<0)なのかな?」
👧 あかり:「うーん、それがちょっと違うんだ。
たとえば y=−x² みたいにaがマイナスのとき、グラフは“下向き(ガッカリ型)”になって、最大値は0になるの。
でも今回の問題は最大値が3って書いてあるよね?
だから 上に開く放物線(a>0) なんだよ。」
👦 ゆうと:「なるほど! つまり“aはプラス”で、上に開くカーブ(放物線)なんだね!」
👧 あかり:「その通り! じゃあ、どこで最大になるかを考えてみよう。
上に開く放物線は、原点から遠いほうでyが大きくなるんだったね。」
👦 ゆうと:「xの範囲が −2 ≦ x ≦ 3 だから、0から遠いのは x=3 だ!」
👧 あかり:「その通り✨ だから、x=3 のときに y が最大の3になると考えるの。
式に代入してみよう。」
👦 ゆうと:「なるほど! a=1/3 だね。
でも、b はどうすればいいの?」
👧 あかり:「bは“最小値”。
ここでチェックするのは、変域に0が含まれているかどうか!
−2から3の間には0が入っているから、x=0のときがグラフの“谷の底”になるんだよ。」
👦 ゆうと:「あっ、つまりy=0が最小値ってことか!」
👧 あかり:「そう! x=0を代入すれば、y=a×0²=0。
だから b=0 になるんだ。」
👦 ゆうと:「じゃあ、まとめると a=1/3、b=0 か!」
👧 あかり:「完璧!✨
ちなみに、x=−2のときも確かに範囲内だけど、“0から遠い方”ではないから今回は最大・最小には関係しないんだ。
つまり、“0を含むとき”は、x=0(谷の底)と0から一番遠いx(山の端)だけを見ればいいの。」
🧩 まとめ
| 求めるもの | 条件 | 結論 |
|---|---|---|
| a | 最大値3をx=3でとる | a=1/3 |
| b | x=0を含む → 最小値はy=0 | b=0 |
👦 ゆうと:「今回の問題、0が入ってるから、最小値=0がすぐわかるんだね!」
👧 あかり:「そうなの! 二次関数では、“0チェック”+“遠い方のx” で答えが決まるんだよ。
これで、迷わず解けるようになるよ。」
💡先生のひとこと
「x=−2」はたしかに範囲内だけど、0から遠い方ではないから最大・最小には関係しません。
変域に0があるときは、“0と0から遠い方”の2点だけを見ればOKです。
このルールを覚えておけば、グラフを描かなくても一瞬で答えを導けます。
0チェックで見抜け!二次関数の最大・最小Q&A(ゆうと&あかりの会話)
- Q1. まず最初に何を確認すればいいの?
-
👦 ゆうと:「解き始めで一番最初に見るのはどこ?」
👧 あかり:「0チェックだよ。xの範囲に0が入っているかどうか!今回は −2≦x≦3 だから 0が入っている。これで“頂点(x=0)が中にある”って分かるから、y=0が最小か最大のどちらかに必ず絡むんだ。」ワンポイント:0が範囲に入る→頂点の値 y=0y=0y=0 が候補に入る。
- Q2. aの符号はどうやって決めるの?
-
👦 ゆうと:「上に開くか下に開くか、どう見分ける?」
👧 あかり:「最大値が3って書いてあるよね。もし a<0(下に開く)なら、頂点が最大値0になっちゃう。最大値が3(0より大)ってことは、a>0 上に開くしかないよ。」ワンポイント:最大が0より大 ⇒ a>0a>0a>0(上に開く)確定。
- Q3. 最大値3はどこで出るの?なぜ x=3 なの?
-
👦 ゆうと:「上に開くなら、どのxで最大3になるの?」
👧 あかり:「“原点から遠い方のx”で大きくなるよ。範囲は −2≦x≦ 33。原点から 遠いのは x=3。だから、\( 3 = a \times 3^2 \rightarrow 3 = 9a \rightarrow a = \frac{1}{3} \)と決まるの。」👦 ゆうと:「じゃあ x=-2 は今回、最大・最小の決定には関係しないんだね。」
👧 あかり:「そう。0を含むときは “x=0” と “0から一番遠い方” が主役。遠くない方(ここではx=-2)は深追いしなくてOK。」ワンポイント:0を含む ⇒ “0” と “遠い方” だけ見れば十分。
- Q4. 最小値bはどう求めるの?
-
👦 ゆうと:「bは最小値だよね。どうやって決めるの?」
👧 あかり:「0チェックを思い出して。0が入っていて、しかも a>0(上に開く)なら、頂点の値が最小。だから x=0で、b=0 で確定だよ。」ワンポイント:0を含み、a>0 ⇒ 最小は y=0。
- Q5. 間違えないための検算は?
-
👦 ゆうと:「本当に \( a = \frac{1}{3} \)とb=0 で合ってるか、不安…。」
👧 あかり:「検算しよう! \( a = \frac{1}{3} \)なら
x=0: y=0(最小候補)
x=3のとき \( y = \frac{1}{3} \times 3^2 \) =3(最大=問題文の上端と一致)
x=-2のとき \( y = \frac{1}{3} \times (-2)^2 = 3 \) =\( \frac{4}{3} \)
変域は確かに 0≦y≦3 ばっちり!」ワンポイント:求めたaで「0・遠い方・もう一方」を代入して、最大最小と中間関係を確認。
最後にひとこと(考え方の合言葉)
「0チェック → aの符号 → 0 と 遠い方」
この3ステップだけで、応用の変域もスッキリ解けるよ!
🧠 先生からの「ここだけは絶対に押さえろ!」
✅ ① まず“0チェック”をする!
x の範囲に 0が含まれているかどうか を最初に確認。
0が入っていれば、y=0が最大か最小のどちらかに必ず関係します。
✅ ② a の符号で“上か下か”を判断!
a>0 なら「上に開く放物線」→ y=0が最小値。
a<0 なら「下に開く放物線」→ y=0が最大値。
✅ ③ もう一方の値は“0から遠い方のx”で求める!
範囲の両端のうち、0から遠い方を使えば、もう一方の端のyが出ます。
近い方(今回のように x=−2 など)は、最小・最大の判定には関係しません。
✅ ④ 0を含むときは、x=0と遠い方のxだけでOK!
中間点やもう一方の端は気にしなくて大丈夫。
「0と遠い方」、この2点だけを押さえれば答えが出ます。
✅ ⑤ “グラフを描かなくてもイメージできる力”をつけよう!
放物線の形を頭に描けるようになると、計算よりも早く「どこで最大・最小になるか」がわかります。
“0チェック → aの符号 → 遠い方”の流れを自然にできるようにしましょう!
👧 あかり:「0と“遠い方”が主役、これを忘れなければ大丈夫!」
👦 ゆうと:「よし、もう“どこを見るか”で迷わなくなりそう!」
🧮 確認練習問題(応用編)
① 関数 y = a x²について、x の変域が −2 ≦ x ≦ 3 のとき、y の変域が b ≦ y ≦ 3 となりました。
a と b の値を求めなさい。
解説:
変域に 0 を含む → y=0 が最小値。
最大値3は、 0 から遠い方の x=3 のとき。 a>0
\( 9a=3 \rightarrow a = \frac{1}{3} \)
✅ 答え:\(a = \frac{1}{3} \), b=0
② 関数y = a x² について、x の変域が −3 ≦ x ≦ 2 のとき、y の変域が b ≦ y ≦ 4.5 となりました。
a と b の値を求めなさい。
解説:
変域に 0 を含む → y=0 が最小値。
最大値2は、 0 から遠い方の x=-3 のとき。 a>0
\( 9a = \frac{9}{2} \rightarrow a = \frac{1}{2} \)
✅ 答え:\(a = \frac{1}{2} \), b=0
③ 関数y = a x² について、x の変域が −1 ≦ x ≦ 4 のとき、y の変域が b ≦ y ≦ 8 となりました。
a と b の値を求めなさい。
解説:
変域に 0 を含む → y=0 が最小値。
最大値8は、 0 から遠い方の x=4 のとき。 a>0
\( 16a = 8 \rightarrow a = \frac{1}{2} \)
✅ 答え:\(a = \frac{1}{2} \), b=0
④ 関数y = a x²2 について、x の変域が −2 ≦ x ≦ 3 のとき、y の変域が −8 ≦ y ≦ b となりました。
a の値と b の値を求めなさい。
解説:
変域に 0 を含む → y=0 が最大値。
最小値-8は、 0 から遠い方の x=3 のとき。a<0
\( 9a = -8 \rightarrow a = -\frac{8}{9} \)
✅ 答え:\(a = -\frac{8}{9} \), b=0
⑤ 関数y = a x²について、x の変域が −4 ≦ x ≦ 2 のとき、y の変域が −8 ≦ y ≦ b となりました。
a と b の値を求めなさい。
解説:
変域に 0 を含む → y=0 が最大値。
最小値-8は、 0 から遠い方の x=-4 のとき。a<0
\( 16a = -8 \rightarrow a = -\frac{1}{2} \)
✅ 答え:\(a = -\frac{1}{2} \), b=0
🌈 未来は君の中にある!
👦 ゆうと:「この問題、最初は意味がわからなかったけど、だんだん“形”が見えてきた気がする!」
👧 あかり:「そうそう!考え方がわかると、数字もすこし楽しくなるよね!」
✨ 勉強って、“わからない”ときは闇の中にいるみたい。
でも、1つ考え方をつかめた瞬間、目の前がパッと開けるんです。
大事なのは「できるようになるまであきらめないこと」。
今日つまずいたところが、明日の成長の入口になるかもしれません。
だから、もし難しく感じても――
「今はその途中なんだ」と自分に声をかけてみてください。
君の中には、まだ見つかっていない可能性がたくさん眠っています。
小さな一歩を積み重ねるたびに、それが少しずつ形になっていく。
🌱 未来は、誰かに与えられるものじゃない。君が作っていくもの。
今日の努力が、その第一歩です。