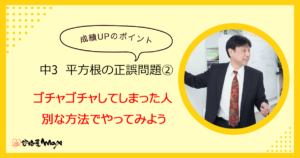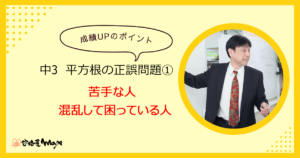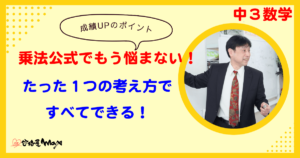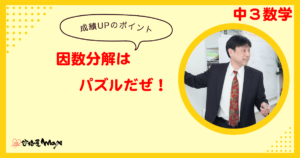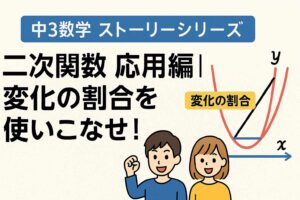中3数学 二次関数の変化の割合とは|公式と意味をわかりやすく解説
変化の割合の公式とグラフの関係
一次関数と二次関数の違いを徹底解説
🎬 スタート💬 ゆうと&あかりのストーリー解説
👦 ゆうと:「ねえ、“変化の割合”って、一次関数のときは“傾き”って習ったけど、
二次関数でも出てくるんだよね? でも、グラフは曲線なのに、どうやって考えるの?」
👧 あかり:「いい質問! 二次関数の“変化の割合”は、一次関数みたいにいつも同じじゃないの。
場所によって、yの増え方が違うから、そのたびに計算して確かめる必要があるんだよ。」
👦 ゆうと:「へえ、同じ式でも場所が違うと結果が変わるんだ。なんか不思議だね。」
👧 あかり:「そうなの。でもね、“変化の割合”そのものの意味がしっかりわかっていれば、二次関数でも怖くないよ。
まずは基本からもう一度整理してみよう。一次関数のときと比べて考えると、違いがスッキリ見えてくるから!」
「変化の割合」って何?一次関数と二次関数のちがいをマスターしよう!
👦 ゆうと:「“変化の割合”ってよく出てくるけど、正直なんだかピンとこないんだよね。」
👧 あかり:「うんうん。じゃあね、まずは“xがどれだけ変わったときに、yがどれくらい変わるか”を見てみよう! 公式はこれだよ! \( \text{変化の割合} = \frac{\text{yの増加量}}{\text{xの増加量}} \)」👦 ゆうと:「つまり、“xの変化に対してyがどれくらい動くか”ってことか!」
👧 あかり:「そう!グラフでいうと、点と点を結んだときの“傾き”を表してるんだよ。」
🧮 一次関数の変化の割合はいつも同じ!
👧 あかり:「たとえば一次関数 y = -2x + 5 を見てみよう。
xが1から4に増えるときの変化を調べるね。」
👦 ゆうと:「xの増加量は 4 − 1 = 3。
x=1 のときは y=3、x=4 のときは y=-3 だから、yの増加量は -3 − 3 = -6 !」
👧 あかり:「つまり変化の割合は -6 ÷ 3 = -2!
この“-2”って、式の中の“傾き a”と同じ値だよ。」
👦 ゆうと:「ほんとだ!y = ax + b の“a”がそのまま変化の割合になるんだ!」
👧 あかり:「そう。だから一次関数は“直線”。どの区間でも傾き(変化の割合)は同じなんだよ。
グラフを見ても、どの2点を結んでも同じ角度になるよね!」
📈 二次関数の変化の割合は変わる!
👦 ゆうと:「じゃあ、二次関数ではどうなるの?」
👧 あかり:「今度は y = 3x² で考えてみよう。
xが1から4に増えるときの変化を調べるよ。」
👦 ゆうと:「xの増加量は3、x=1のときy=3、x=4のときy=48だから、
yの増加量は 45。変化の割合は 45 ÷ 3 = 15 !」
👧 あかり:「いいね!でもここが大事なポイント!
二次関数では、区間が変わるたびに変化の割合も変わるの。
👦 ゆうと:「なるほど!同じ式でも、場所が違えば“増え方”も変わるってことか!」
👧 あかり:「そう。二次関数のグラフは“曲線”だから、
場所によって傾き(変化の割合)が変わるんだ。
左側ではマイナス、右側ではプラスになることもあるよ。」
💡 あかりのまとめ
| 種類 | 変化の割合の特徴 | グラフの形 |
|---|---|---|
| 一次関数 | どの区間でも一定(傾き a と等しい) | 直線 |
| 二次関数 | 区間によって変わる。毎回公式で計算が必要! | 放物線 |
👦 ゆうと:「なるほど! “まっすぐ”だと変化の割合はずっと同じ、
“曲がってる”と場所で変わるってことだね!」
👧 あかり:「その通り! グラフを見れば“変化のしかた”が一目でわかるんだよ。
そして二次関数では、その都度ちゃんと計算して確かめるのがコツなんだ。」
❓Q&Aで「変化の割合」の考え方をマスターしよう!
- Q1:👦 ゆうと:「一次関数の変化の割合って、なんでいつも同じになるの?」
-
👧 あかり:「いい質問!一次関数のグラフは“まっすぐな線”だからだよ。
どの区間でも傾き(上がり方・下がり方)が同じなんだ。
xが1増えたときのyの増え方が、どこでも一定ってことだね。」 - Q2:👦 ゆうと:「二次関数では、どうして変化の割合が変わるの?」
-
👧 あかり:「二次関数のグラフは“曲線”だからね。
だから、その都度\( \text{変化の割合} = \frac{\text{yの増加量}}{\text{xの増加量}} \)を計算して確かめる必要があるんだ。」
xの場所によって、yの増え方が違うの。 - Q3:👦 ゆうと:「“増加量”ってどうやって見つければいいの?」
-
👧 あかり:「xの増加量なら『あとのx − もとのx』、yの増加量なら『あとのy − もとのy』、
で出すんだよ。順番を逆にすると符号が変わっちゃうから注意ね!」 - Q4:👦 ゆうと:「変化の割合がマイナスになるのは、どんなとき?」
-
👧 あかり:「それは“右に進むほど下がる”とき!
たとえば一次関数のy = -2x + 5みたいに、xが増えるとyが下がる関数だと、
変化の割合はマイナスになるんだ。
グラフの線が右下がりなら、変化の割合はマイナスって覚えるといいよ。」 - Q5:👦 ゆうと:「二次関数の変化の割合を調べるとき、どんなところに気をつければいいの?」
-
👧 あかり:「いちばん大事なのは、どの区間を調べるかをはっきり決めること!
xが1から2なのか、2から3なのかで、結果がまったく違ってくるの。
あと、増加量の計算ミスにも注意ね。特にマイナスのときは符号を落としやすいから!」
👧 あかり:「“変化の割合”って、ただの計算じゃなくて、
“グラフがどう動くか”を読む力を育てる問題なの。
数式の裏にある“動き”をイメージできるようになると、
数学がぐっと面白くなるよ!」
🧠 ① まず「意味」をつかもう!
- 変化の割合とは?
→ xが増えたとき、yがどれだけ増える(または減る)かを表す数字。
つまり「グラフの傾き」を表している。 - 一次関数では?
→ どの区間でも“傾き”は一定。だから、どこで調べても同じ値になる。 - 二次関数では?
→ グラフが、曲がっている(放物線と双曲線)場合は、場所によってyの増え方が変わる。
そのため、区間ごとに計算して確かめる必要がある!
✏️ ② 公式はこれだけ覚えよう!
\( \text{変化の割合} = \frac{\text{yの増加量}}{\text{xの増加量}} \)- 「あと − もと」で増加量を出す!
→ yの増加量 = あとのy − もとのy
→ xの増加量 = あとのx − もとのx - マイナスを間違えると結果が逆になるので注意!
例: もとの数が-2の時は、あとの数 −( -2)と計算する。
📈 ③ グラフのイメージを持とう!
- 一次関数:直線 → 一定の傾き
- 二次関数:放物線 → 傾きが場所によって変わる
➡ 右側(xが大きい方)では上に急に上がる。
➡ 左側(xが小さい方)では下がることもある。
💬 ④ よくある間違いトップ3!
| よくあるミス | 修正ポイント |
|---|---|
| xとyの増加量を取り違える | 「あと − もと」の順序を徹底 |
| 二次関数でも a を変化の割合と誤解 | 毎回「yの増加量 ÷ xの増加量」で計算 |
| 分子分母を逆にする/符号ミス | 分母=xの増加量,分子=yの増加量を確認 |
🌟 ⑤ 最後に
👨🏫 変化の割合は、“どんな動きをしているか”を考えることが大事!
「上がってる?」「下がってる?」「ゆっくり?」「急に?」
そうやって“グラフの気持ち”を感じ取れるようになれば、
二次関数はもう怖くありません。
🧮 変化の割合・確認テスト(基本10題)
① 関数 y=3x+2 のとき、xが1から4まで増加するときの変化の割合を求めよ。
答え: 3
解説: 一次関数では変化の割合=傾きa。
よって、どの区間でも常に3。
② 関数 y= x² のとき、xが1から3まで増加するときの変化の割合を求めよ。
答え: 4
解説: xの増加量 =3−1= 2 yの増加量 = 9 − 1 = 8
③ 関数 y=5x−4 xが2から5まで増加するときのyの増加量を求めよ。
答え: 15
解説: xの増加量 = 5−2=3 yの増加量=21−6=15
④ 関数 y = 2x² のとき、xが0から2まで増加するときの変化の割合を求めよ。
答え: 4
解説: xの増加量 =2 − 0 = 2 yの増加量 = 8 − 0 = 8
⑤ 関数 y = 3x²のとき、xが1から4まで増加するときの変化の割合を求めよ。
答え: 15
解説: xの増加量 = 4 − 1 =3 yの増加量 = 48 − 3 = 45
⑥ 関数 y = 3x² のとき、xが -3 から -1 まで増加するときの変化の割合を求めよ。
答え: -12
解説: xの増加量 = -1 −(-3) =2
yの増加量 = 3(−1)² − 3(−3)² = 3 − 27 = -24
⑦ 関数 y = -2x + 5 のとき、xが0から3まで増加するときの変化の割合を求めよ。
答え: -2
解説: 傾きが -2 なので、変化の割合は -2。
一次関数では区間を変えても、傾き(変化の割合)は一定。
⑧ 関数y = 2x² のとき、xが -2 から 0 まで増加するときの変化の割合を求めよ。
答え: -4
解説: xの増加量 = 0 −(-2) = 2 yの増加量 = 0 − 8 = -8
⑨ 関数 y = x² のとき、xが -1 から 2 まで増加するときの変化の割合を求めよ。
答え: 1
解説:xの増加量 = 2 −(-1)=3 yの増加量 = 4 − 1 = 3
⑩ 関数y = 4x² のとき、xが2から3まで増加するときの変化の割合を求めよ。
答え: 20
解説: xの増加量 = 3 − 2 =1 yの増加量 = 36 − 16 = 20
🌈 「変化を恐れず、自分のペースで進もう!」
📘 締めの言葉&激励メッセージ
「変化の割合」を考えることは、
実は“自分の成長の変化”を見つめることにも似ているかもしれません。
最初はなかなかうまくいかなくても、
少しずつ積み重ねていけば、必ず“上がるカーブ”を描いていく。
グラフの線がだんだん上がっていくように、
努力は、確実に上へと伸びているんです。
👧 あかり:「変化は怖くないよ。大事なのは“比べること”じゃなくて、“進むこと”。」
👦 ゆうと:「そうだね。自分のペースで少しずつでも前に進めば、それが一番の成長だ!」
焦らず、コツコツと。
今日できなかったことが、明日はできるようになる。
その積み重ねこそが、一番の力です。
今日の“わかった!”が、明日の自信につながる!